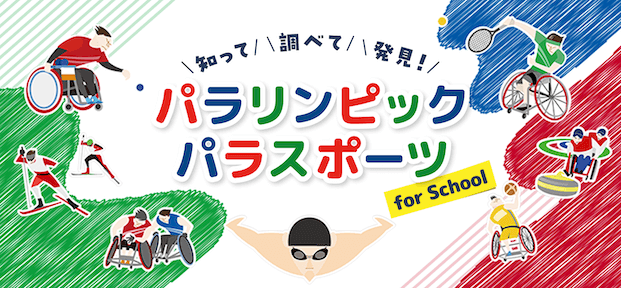子どもの体力向上、健康増進、将来の可能性拡大……実現の鍵は、体力テスト記録のデジタル化にあった!?

反復横跳びや50メートル走、ソフトボール投げなど、文部科学省の定めた種目を行って体力のレベルを測る体力テスト(正式名称は「新体力テスト」)。小学1年生から高校3年生まで、毎年1回、約1200万人の児童生徒が取り組んでいるが、結果は紙に手書きのアナログな方法で記録されるケースが多く、有効活用できていないという。そのデジタル化を進めているのが、Pestalozzi Technology株式会社(以下、ペスタロッチ社)だ。この記録のデジタル化は、我々にどのようなメリットをもたらすのかを、同社社長の井上友綱氏に聞いた。
データのデジタル化で運動へのモチベーションもアップ

日本で小学校から高校まで、年に1回8種目で行われる体力テストの歴史は古く、1964年の実施が最初だ。生徒が自分の記録を各自で紙に記入し教師に提出すると、教師が手作業で入力しExcelにまとめたり、専門業者に委託したりするなどして集計し、紙の個人結果票として生徒に後日渡すという方法で長年続けられてきた。その体力テストの入力・集計・結果分析までをデジタル化できるようにしたのがペスタロッチ社の開発したウェブサービス“ALPHA(アルファ)”だ。
児童生徒は、それぞれの端末からWebブラウザを立ち上げて、ALPHAのサイトにアクセスしてログインを行い、身長・体重を入力した後、テストの結果を打ち込んでいく。するとすぐに結果の評価やアドバイスなどが表示されるほか、それぞれのレベルにあわせたおすすめの運動の動画なども見ることができる。現在全国で4200校、約160万人が利用している(2024年実績)そうだが、ALPHAのどんな点がユーザーから喜ばれているのだろうか。
「まず、児童生徒の観点から言うと、これまではテストの結果の集計に数週間から数ヶ月かかっていたので、テスト直後の高いテンションがだいぶ下がってしまって関心もかなり薄れた頃に結果が返ってきます。そのため結果を見ても“なんだ、自分はこんな感じだったか”程度で終わっていました。しかし、ALPHAが導入されると、測定前に昨年の結果を見て今年はここまで頑張ろうと目標を立てたり、測定後もすぐに個人結果票が出るので、来年へのモチベーションに繋がったりします。また結果に応じて、個別に最適化された運動を動画で提案もしているので、一番運動に興味があるタイミングで、自分が何に取り組んだら良いかがわかる。運動習慣が付きやすい環境を提供できているのではないかと思います」
そう語るのは、“運動データを価値あるものに”というビジョンを掲げ、2019年に創業したペスタロッチテクノロジー株式会社の社長・井上友綱氏だ。もちろんALPHAは、“働き方改革”の流れの中、教師の負担軽減にも大きく寄与している。
「たとえば、生徒の手書きだとこの数字は0か6かわからない……とか、記入のない箇所があって個別に確認したり、全員から紙を集めたはずなのに何枚かどこかにいってしまったり、水に濡れてしまったりなど、とにかく大変です。でも、ALPHAなら教師用のアプリの画面ですぐに児童生徒が入力した結果を確認できますし、効率化、負担の減少に繋がっていると評価いただいています」(井上氏、以下同)
また、児童生徒用同様に、教師用にも体育の授業で使える運動動画が用意されているそうだ。これは、一人の教師がいろいろな授業を受け持ち、必ずしも体育を専門に勉強してきた教師ばかりではない小学校では喜ばれるコンテンツに違いない。

米国アメフト界では選手のスカウトにデータを活用

そもそも井上氏が、このような体力テストのデータに着目し、“運動データを価値あるものに”というビジョンを掲げて起業したのには、高校時代からアメリカンフットボールの選手として活躍し、早稲田大学を卒業後アメリカに渡り、NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)に挑戦していた時の経験がきっかけになっている。
「アメリカのアメフトの世界では、選手の身体能力を測るテストがあって、スコアを入力するとデジタルでデータベース化されるというシステムが整っていました。ですから、たとえば大学チームのリクルーターが高校生をスカウトするときに、このデータベースを上手く利用して、地方に埋もれている優秀な選手を発掘するというようなことが可能だったのです。高校生の未来を広げるという意味でも、このようなシステムは重要だなと思い、帰国後、運動データのデジタル化に取り組むことにしました」
ただ、アメリカに比べて、日本はまだまだスポーツビジネスの市場は大きくはない。プロスポーツの世界でビジネスとして成立させるのは難しいかもしれない、と思ったときに着目したのが、小学校から高校まで行われている体力テストだったのだ。
「アメリカでは、大学に進学したくてもできない高校生が、体力テストのデータベースを通じて能力が発見され、進学の機会を持つことができています。日本でも、子どもたちの可能性を広げるために何かをしたいという気持ちがあったので、いろいろ調べていました。そんなときに文部科学省のGIGAスクール構想が発表され、1人1台端末を持つ環境の実現を目指すことになりました。ALPHAの誕生はそんな状況に背中を押された面もあります」
0歳から100歳以上まで、ヘルスケアやメディカル領域にも活用は広がる

実は、ALPHAのメリットは学校の教師や児童生徒だけではなく、児童生徒の家族にももたらされている。
「親御さんから、自分たちもALPHAを使っているという声をいただくようになりました。ある方は、娘さんが“自分は反復横跳びが得意じゃないんだけど、ここに練習の動画があるから、パパ一緒にやろうよ”と誘われたのだそうです。お父さんも娘さんに付き合って運動するきっかけができてよかったと。子どもたち起点でコミュニケーションが生まれて、児童生徒だけではなく大人にも運動の機会が広がっていくのは、我々にとっても喜ばしいことですね」
子どもの体力低下が問題になって久しいが、それは子どもに限ったことではない。“人生100年時代”と言われる一方で、いかに健康寿命を延ばし、寿命と健康寿命の差を縮めるかは誰にとっても大きな課題だろう。ペスタロッチ社は今年3月、社内研究機関として「日本健康・運動データ総合研究所」を設立した。これはまさに、“運動データを価値あるものに”という同社のビジョンを、学生領域だけではなく、0歳から100歳まで、いや100歳以上にまで拡大して、健康な人を増やしていくことに繋げる取り組みになるのではないだろうか。
「小学生から高校生までの体力テストのデータをデジタル化し蓄積していくことによって、いろいろな発見がありました。まさに価値があるデータなので、今後は社会的意義を追求し、研究にも力を入れていくために“日本健康・運動データ総合研究所”を設立しました。体力テストは、高校を卒業すると測定しなくなるので、今後社会人や高齢者のデータをどうやって取っていくかというのは課題ですね。各健保組合と連携し、企業の社員の健康診断と同じタイミングで運動能力を測定するとか、自治体と組んでイベントを開催するなどして一般の方、高齢者のデータを取っていくという方法もあるかと思います。そのようなデータを蓄積して、ユーザーの方々に価値を届けたり、研究発表をしたり、政策提言なども行ったりしていきたいですね」
ALPHAが実現するのは、児童生徒の体力テストの結果のデジタル化だが、身長・体重や、スポーツの好き嫌い、普段の日々の過ごし方などのアンケートを通じて見えてくるものは、ヘルスケアやメディカル領域にも価値を発揮する。たとえば、女性の将来の妊娠・出産に影響する可能性がある“痩せ過ぎ”の予防、低身長症などの小児疾患の早期発見などにも、ALPHAは効力を発揮するという。運動データの価値には、まだまだ多くの可能性が秘められているようだ。
地震など自然災害の多い日本では、被災した人々の健康管理にも課題がある。能登半島地震では、学校のグラウンドに仮設住宅が建てられ、運動する場所もなければ、地震による環境の変化で運動の機会も減っているという。ペスタロッチ社は、この能登地域とも2025年度に連携協定を結んで、体力向上、健康増進に取り組んで行く予定だそうだ。また、通常の体力テストの実施が難しい障がいのある児童生徒に対しても、個々の状況に応じた最適な評価についての共同研究が進められている。井上氏の展望には、単なるDX化による効率アップ、省力化にとどまらない価値が確かにあると実感できた。
text by Reiko Sadaie(Parasapo Lab)
photo by Shutterstock
写真提供:ペスタロッチテクノロジー株式会社