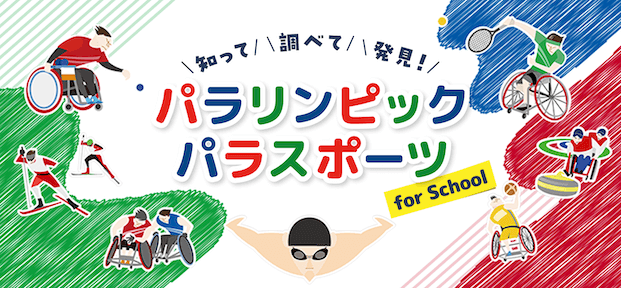ゼロからのチームづくりで日本一!健大高崎高校野球部監督が語る、勝てる組織づくりの根幹は「人の和」

2024年、春のセンバツ高校野球で優勝した群馬の高崎健康福祉大学高崎高等学校(以下、健大高崎)。グラウンドも満足な道具もない野球同好会から始まった弱小チームが、創部から22年で甲子園優勝を果たした組織づくりにあったものとは? 同校の野球部を創部から現在に至るまで率いる青栁博文監督に話を聞いた。
バット3本、ボール1ダースしかなかった弱小野球部から甲子園優勝へ

青栁監督が高校野球の指導者を目指してサラリーマンを辞め、同校に教員として採用され、同時に硬式野球部の監督に就任したのは2002年の春。しかし前年の2001年に女子校から共学になったばかりだったため、男子生徒は2年生と入ったばかりの1年生のみ。しかも、できたばかりの野球部には専用のグラウンドがない上に、バットは3本、ボールも1ダースしかなかった。そんな中、青栁監督は野球部の最初のミーティングで「本気で甲子園を目指そう」と熱い言葉で語りかけた。そうした熱血ぶりが空回りし、部員が減ってしまうこともあったそうだが、諦めず練習を続け、ようやく夏の大会出場という最初の一歩を踏み出した。しかし、ここでもショックなことがあった。
「大会を機に、校名の入った野球バッグを作ったんですが、みんな校名を裏にして自転車の籠にのせていました。当時は男子生徒のほとんどが公立高校の受験に失敗して入学してきていたので、劣等感を持っていた。さらに満足な設備もなく周囲からは健大高崎は草むらで練習をしているなどと陰口をたたかれていたため、校名を隠したいという心境だったと思うんです。ですから、まずは自分の通う学校に誇りを持ち、正々堂々と健大高崎の野球部員と言えるようにしてやりたいと考えたんです」(青栁監督)
甲子園で日本一を経験した今も、青柳監督のこの思いは変わっていない。周囲から愛され応援される野球部であること、それを誇りに思える選手であることは、チームが強くなるためには大切なことだという。そしてこれは野球だけでなくどんな組織にも通じることだろう。人は誇りに思えない組織で全力を発揮することはできないし、ましてやしたいとも思えないからだ。
「不如人和」団結は全てに勝る

健大高崎の野球部といえば「機動破壊」という戦術スローガンが有名だ。2010年夏の群馬大会準決勝、初の甲子園出場を目前としたこの試合で、同校は前橋工業高校に0対1で敗れた。そこで翌年には「機動力(盗塁などの走力)」によって「(相手の試合運びを)破壊」する戦術を打ち立て、さらに翌年の2012年にはこの戦術を生かし、見事初のセンバツ出場を果たした。そして「機動破壊」を掲げて出場した甲子園ではベスト4となり、このスローガンと共に一気に健大高崎の名が全国に知れ渡った。
そして戦術と合わせてもうひとつ健大高崎の野球部が大切にしているのは「不如人和(ふにょじんわ・人の和に如かず)」というスローガン。これは「団結(人の和)はすべてに勝る」という孟子の言葉で、青栁監督は人の和を何よりも大切にしている。
「『不如人和』はうちの柱で、チームワークを乱すことは絶対に許さないと、1年生の時から徹底的に教えます。たとえば中学で野球がうまいと言われていた子は、俺が一番いい選手だと、お山の大将のように勘違いしているケースがあります。でもうちでは、どんなに野球がうまくても、ワガママだったり、チームの和を乱したりする子は試合には出しません。
しっかり対話をして、チームのために一人ひとりが動くのがうちの野球。場合によってはチームのために4番でもバントをするような犠牲心も必要だという話をします」
監督やコーチのこうした教え、さらには先輩たちの言動から選手たちは自然と人の和の大切さを学び、チームの団結力が強まっていくという。
また、選手だけでなく指導陣も人の和を大切にしている。通常は監督のほかに2~3人のコーチのところ、健大高崎の指導者は監督や外部のコーチを合わせて12人。それぞれの分野のスペシャリストが指導を担当するそうだが、こんなに大勢の指導者がいてかえって混乱することはないのだろうか。

「私は自分に力があるとは思っていないので、いろいろな人の力を借りることにしたんです。そして、力を借りるからには任せきることが大切です。もちろんチームとしての柱がぶれないようにコミュニケーションは取りますが、たとえば二軍戦や三軍戦でどの選手を使うのかとかといったことは全てコーチに任せます。もし監督の私が中途半端にコーチたちに指示をすれば、相手も面白くないですよね。もし任せてうまくいかないことがあれば、それは任せた私の責任。それくらいの覚悟を持って任せています」
しかし、監督も人間だ。最初の頃は、直接指導をしているコーチが選手たちから「コーチ、コーチ」と慕われている場面を見て、羨ましいと感じたこともあるという。しかし、本当に勝てる組織をつくる、という目的を明確にした時から、そんなマイナスな感情はなくなったそうだ。こうした「不如人和」の考えが健大高崎の団結力を強め勝利へと導いたのだ。
60人分の野球日誌を毎日チェック

そんな青柳監督と選手達の大切なコミュニケーションとなっているのが野球日誌だ。60人の部員が全員、A4サイズのノートに半ページほど、その日あったこと、反省点などを書き提出。それをチェックするのだそうだ。
「パソコンやスマホが普及している現代、子どもたちも、文章を手書きする機会が非常に少なくなっています。しかし、自分の考えを客観的にまとめて文章にする作業は、人が成長する上でとても大切なことです」
野球日誌は内容をチェックするのはもちろん、漢字などの間違いも指摘するという。
「分からない漢字をスマホで調べられるのに、そうした簡単なことを疎かにするのはダメだと注意します。スマホで打つのではなく手書きすることできちんと覚えることができますから」
日誌を毎日書かせてチェックすることは大変だが、選手たちとのコミュニケーションにもなるのはもちろん、彼らが受験をする際の小論文のテストにも役立つとの考えから毎日続けている。
たとえ監督が不在でも変わらぬ組織づくりを

野球に限らず高校の部活動の場合、どんなに能力のある選手でも卒業と同時に引退。毎年のようにレギュラーメンバーは入れ替わる。そうした新陳代謝の激しい組織をどうやってまとめ、強いチームにしているのだろうか。
「ひとつは、誰が監督をしても勝てる組織をつくることです。たとえば、私がある日突然死んでしまったとしても、それまでと変わらぬ組織づくりを心がけています。会社の社長が交代をしても会社というのはその先も続くわけですが、それと同じです。ですから、私がやっていることをコーチ陣が代わりにできるようにしておくこと。そのために、日頃から細かいコミュニケーションは欠かしません」
そしてもうひとつ大切にしているのは、どんな選手にも公平にチャンスを与えるということ。センバツ優勝校となった健大高崎には有望な選手が多く集まる。だからといって、その選手を特別扱いするようなことはない。
「投手だけでも、3年生が卒業した3月は1~2年生だけでピッチャーが16人ほどいます。練習試合ではピッチャー全員が必ず投げるようにローテーションを組みます。勝つために強い選手だけを使うということはありません。土日に練習試合があれば、全員が均等に投げられるようにシフトを組むことで、いい意味で競争意識を高めることになり、みんが自分にもチャンスがあると頑張れるんですね」
平等なのはチャンスだけではない。昭和のような厳しい先輩後輩の関係はなく、部内の当番やボール拾いも学年に関係なく平等に分担し、後輩たちは身近で先輩たちの姿を見ながら、さまざまなことを学んでいくのだそうだ。
「機動破壊」で一躍有名になった健大高崎だが、昨年のセンバツで同校の盗塁はたったの1回。これに関して青栁監督は「機動破壊は弱者の戦略です。当時のうちの野球部にはそれしかありませんでした。でもいつまでもそれだけでは、勝ち残れません。ですから機動破壊は一つの攻撃のパターンとして残しつつも、選手の技量に見合った戦い方をしなければ日本一にはなれません」と話す。と同時に「野球戦術は日々進化していく、でも不如人和という精神に関しては変わらぬ組織をつくっていくことが大切」と語る。
バット3本とボール1ダースから始まった同校の野球部も今では敷地内に、ナイターもできる野球専用グラウンド、野球専用室内練習場、合宿所、トレーニングルームなどを擁する大きな組織になった。しかし、そこには創部当時から変わらない、「人の和」「団結」を大切にする監督のブレない信念がある。この強い信念があるからこそ、柔軟にできるところは柔軟にする。それが、健大高崎の強さの秘密なのではないだろうか。
text by Kaori Hamanaka(Parasapo Lab)
写真提供:高崎健康福祉大学高崎高校