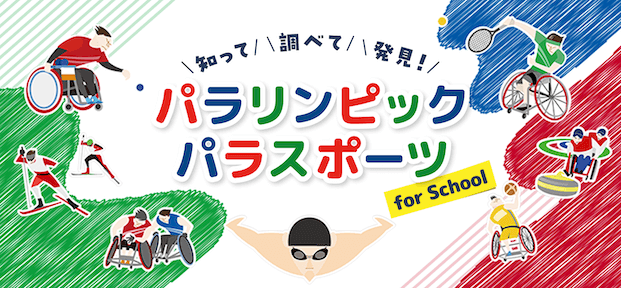インクルーシブ教育は“特別”ではない。先生一人からでも始められる、みんなのための教育

「インクルーシブ教育」は、子どもたちの今、そして未来にとって大切な教育だということを先生方も感じているのではないでしょうか。
ただ、導入における人的リソースやシステムの導入、コストなど多くの壁が立ちはだかり、忙しさも相まって立ち止まってしまう先生も多くいるのではないかと思います。
この記事では、少しずつでも「インクルーシブ教育」に取り組んでいきたいと思っている先生へ向けて、「一人からでも始められるインクルーシブ教育」についてご紹介します。
【この記事を読んでわかること】
☑先生一人でも始められるインクルーシブ教育の考え方・実践例
☑インクルーシブ教育は、共生社会づくりにどのようにつながるのか
先生一人でも始められるインクルーシブ教育の考え方・実践例

インクルーシブ教育は、教育現場の中でどのように行われているのでしょうか。先生一人でも始められる、具体的かつ印象的な実践例を、インクルーシブ教育の専門家であり、ノートルダム清心女子大学准教授の青山新吾氏が挙げてくださいました。
「目の前の子どもたちに対して、一人の教育者としてできることが確実にあると思います。そのうちの一つが違いや多様性に対して、大人として感度を上げて、いろいろなことに疑問を持ったり、子どもたちにもその疑問を投げかけてみること。諦めずに自分の範疇の中で多様性や違いの感度を上げた実践を積極的に取り入れていくといいと思います。
多様性を前提とした学級づくりをしていくポイントは、集団の自治といいますか、自分たちのことをみんなで考えて解決していくことですね。そういうことを小さい頃から大切にしていく考え方は、インクルーシブ教育とすごく親和性が高いと思います」
事例①
ある小学校低学年のクラスの例ですが、ドッジボールが流行っていました。そのクラスには障がいのある子がいて、ドッジボールをやっている所を見に来るんだけど、当てられるのが嫌だから参加はしないと。そこでどうすれば一緒に遊べるかを、本人を含めてクラスのみんなで相談したらしいんです。すると、誰でも入ることができて、尚且つ、ボールを当ててはいけない安全地帯を作ろうと考えたそうなんです。先生がこうしようと言ったわけではなく、児童みんなで考え出した。そうしたらその障がいのある子も参加するようになりました。
「この事例のように、素朴な取組からでいいので子どもたち自身が自分たちのことを考えて、自治的に課題を解決していくことが大切なのです」
事例②
ある小学校6年生のクラスでは、ひとりの女子が不登校傾向の子に連絡の手紙を届けに行っているのですが、それが頻繁になり、困っているとのことでした。仮に、不登校傾向の子をリカさん、議題提案者をケイコさんとしましょう。ケイコさんは、こんな話をしたらみんなに「ひどい人」だと思われると思って議題に出すことを躊躇したようですが、担任に励まされ、話し合うことにしました。担任も悩んでいたようで、子どもたちに相談するしかないと腹をくくっていたようです。話し合いの日もリカさんのお家からは、遅刻するとの連絡が入っていました。リカさんは、低学年の頃から冬になると学校に来られなくなる日が増え、年によっては3学期はほとんど登校できない状態になることもありました。
詳しくケイコさんに話を聞いてみると、自分も弟の迎えがあったり、塾があったりで手紙を届けるのが夕方遅くなるとのことです。季節は冬で暗い雪道を毎日のように届けるのは暗いし寒いし、正直言ってつらい。そして、何よりもこうしたことをつらいと思っている自分を責め続けていたようです。その話を聞きながらクラスメートたちは気づくのです。「リカさんのことをケイコさんだけに任せっきりだった」ということに。最初は男子を中心に「別に…」という空気を漂わせていた子どもたちが、解決策を出しているうちに、だんだんと議題を自分事として問題をとらえ始めました。そして話し合いが盛り上がっているところに、なんとリカさんが「おはようございます」と言って入ってきました。議題は、表向き「欠席連絡カードを届けるのが同じ人ばかりならないようにするにはどうするか」ということになっていますから、リカさんも事態を理解すると自分も解決策の提案者として意見を言っていました。
さまざまな意見が出ましたが、子どもたちが選択したのは、「名簿順で交代で欠席者に電話をかけて連絡をする」というものでした。実はこの決定が、リカさんに大きな変化をもたらします。この話し合いは、12月の初めだったのですが、それからもリカさんの遅刻や欠席は続きました。すると決定通り、クラスメートが交代で電話をかけました。すると、リカさんは、今までほとんどケイコさんとしか話をしていなかったのが、クラスの不特定多数と話すことになったのです。
そしてリカさんは学校に少しずつ来るようになり、登校すると、お友達と話したり遊んだりする様子が見られるようになりました。大切なのは、その子の自分らしさを尊重しながら焦ることなく見守りながら育てていくことです。
「先生方、特に若い先生たちは、とにかく実践して、子どもとこうやって一緒に取り組んでいったら、子どもも自分自身も成長するんだというプロセスを実感することが大切なんじゃないかなと思います」
PROFILE 青山新吾(あおやま・しんご)
1966年兵庫県生まれ。ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授、同大学インクルーシブ教育研究センター長。岡山県内公立小学校教諭、岡山県教育庁指導課、特別支援教育課指導主事を経て現職。臨床心理士、臨床発達心理士。著書に青山氏が編集代表を務める『インクルーシブ教育ってどんな教育?』や岩瀬直樹氏との共同著書『インクルーシブ教育を通常学級で実践するってどういうこと?』、『エピソード語りで見えてくるインクルーシブ教育の視点』(すべて学事出版)ほか多数。
インクルーシブ教育は、共生社会づくりにどのようにつながるのか

日本のインクルーシブ教育システムや世界のインクルーシブ教育のシステムにおける具体的な制度や仕組みに違い(※)があるものの、日本も世界も目指すところは「共生社会」の実現です。
では、インクルーシブ教育は、共生社会づくりにどのようにつながるのでしょうか。
※仕組みの違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください
https://www.parasapo.tokyo/topics/104693
「共生社会とは?」
我々は、障害の有無にかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を実現することを目指している。この共生社会は、様々な状況や状態の人々がすべて分け隔てなく包摂され、障害のある人もない人も、支え手側と受け手側に分かれることなく共に支え合い、多様な個人の能力が発揮されている活力ある社会である。
出典:ユニバーサルデザイン2020行動計画「Ⅰ.基本的考え方」
「身近な人と関係性を築いていくことは、共生社会づくりの一つなのですが、そこにインクルーシブ教育が貢献していくと思います。(インクルーシブ教育で育ったか、そうでないか、その差によって)他者の“違い”に対する感度(他者の“違い”を受け入れられる感度)といったものに、決定的な違いが生まれる。インクルーシブ教育は、そういう感度の良さというところに繋がっていく可能性があると思っています」
例えば、小学校の頃に障がいのある子と同じクラスだった、といった経験が「共生社会の形成基盤」につながると青山氏は言います。具体的なエピソードを紹介してくださいました。
事例③
私は元々、小学校の現場にいたので教え子が多いのですが、キャリア上、知的障がいや自閉症スペクトラムのお子さんをもつ親御さんとの付き合いも多いんですね。これはその中のある親御さんに聞いた話です。
知的障がいがあるお子さんが成人して就職することができ、毎日職場に通っていました。でもある日、いつも帰ってくる時間に帰ってこず、スマホに電話やメールをしても返事がない。何か起きているのかもしれない、どうしようと考えていたら、ピンポンと家の呼び鈴が鳴ったそうです。玄関を開けたら、お子さんと二人の若い男性が立っていて、その男性が「おばちゃん、久しぶり!」と。それで「ああ!小学校のときの〇〇君と〇〇君!」と、お子さんと同級生だった子だと分かったそうなんです。でもなんで一緒にいるんだろうと聞いたところ、駅でギャーギャー騒いでいる人がいて、よくよく見てみたら小学校のときに同じクラスだった〇〇だと気づいたそうです。それで話しかけて落ち着かせ、一緒に歩いて家に連れてきてくれたということでした。
その話を聞いたときに、この若い男性のように、学校で一緒に学び、生活をしたということは後々まで活きていくんだと思ったんです。知っている人に会ったときに友達ですと言ってくれる人が、同じ地域の中にいることの意味を考えさせられたエピソードとして、この話はすごく印象に残っています。
インクルーシブ教育に取り組む中で生まれた「新しい運動会」

日本財団パラスポーツサポートセンターでは、学校の運動会にインクルーシブな種目を導入する「パラサポ!インクルーシブ運動会」を提案しています。
児童生徒や先生は、練習から本番にかけて柔軟な発想と工夫をすることで共生社会への気づきを得て、運動会本番では、保護者や地域の方々にもインクルーシブな考え方が芽生えます。
「パラサポ!インクルーシブ運動会」について詳しく知りたい方はこちら
https://www.parasapo.tokyo/inclusive_undokai/
text by Mariko Amano(Parasapo Lab)
photo by Shutterstock, Haruo Wanibe