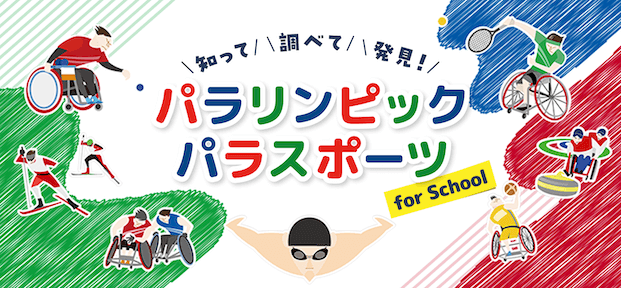-
-
Sports /競技を知る
-

-

-
【共に戦うパラスポーツギア】「軽さ」と「丈夫さ」の両立を目指す、ノルディックスキーの<シットスキー>

パラスポーツの土台には、「失われたものを数えるな。残されたものを最大限に活かせ」という“パラリンピックの父”の教えがあります。そこで重要な役割を果たすのが、選手の最高のパフォーマンスを引き出す用具です。ここでは、ノルディックスキーの「シットスキー」にフォーカス。どんな工夫が隠されているのでしょうか。
素材で変わる重量とコスト
シットスキーは、座った状態でスキーを滑るための用具です。ノルディックスキー(クロスカントリースキー、バイアスロン)で使われます。クロスカントリースキーは坂道や平地を滑り、速さを競います。バイアスロンは、滑るだけでなく射撃も行う競技です。
シットスキーは、アルミでできたフレーム、シート、ベルトでできていて、フレームの下にスキー板を2本取り付けて滑ります。また、ストックを手に持ち、雪の上を滑るときにバランスを取ったり、雪面を突いて進んだりします。
日本代表として世界選手権などで活躍する源貴晴選手のシットスキーを見ながら学んでみましょう。

選手が用意する用具の例
・シットスキー
・スキー板:2本使います。
・ベルトやクッション:姿勢を安定させるほか、体とシートをフィットさせるために使います。選手たちはそれぞれで工夫しています。

シットスキーは「軽さ」と「丈夫さ」のバランスが大切。軽ければ身体との一体感は高まりますが、軽くするにはパーツを細くしたり薄くするため、その分強度が落ちてしまいます。競技中は衝撃が大きいので、ヒビが入ったり割れたり折れたりすることもあります。「軽くて丈夫」を両立するため、まず形を決めてから、余分な部分を減らして軽くしていくのが基本です。見た目では分かりにくい変化でも、乗った選手は軽さを実感するそうです。なお、源選手のシットスキーは約2.5kgです。
素材の違いと特徴
・木製:価格は安いが重い
・アルミ(アルミ合金):修理しやすく丈夫。12〜40万円ほどで普及用にも向く
・カーボンファイバー:軽くしなやかで衝撃に強い素材。ただし200〜300万円と一番高価
世界のトップ選手は、カーボンファイバー製を使っている選手もいますが、日本選手はアルミ合金製が中心。国内では北海道で製作され、強化合宿中に選手が試しながら調整できる体制が少しずつ整ってきています。
選手の特徴に合わせてチューンナップ
シットスキーは、身体の動かし方や状態に合わせてシートの角度を変えたり、ベルトを増やしたりする工夫がされています。

例えば、上半身の力が強く、腹筋を使える選手は、少し立ったような姿勢(ひざ立ちに近い形)にして、腕の力を使いやすくします。腹筋にまひがある選手は正座に近い姿勢にします。
ひざの動きに制限がある人や筋肉が硬くなりやすい人(けい性がある人)には、痛くならない、力が入りすぎない角度を何度も試しながら調整します。
ひざから下がない人は、しっかり固定する特別なパーツ(ソケット)を付けることもあります。


シートにはアルミ板、硬いナイロン、軟らかいプラスチックなどが使われます。
お尻全体を包み込むような形のシートもあり、安定感に優れていますが高額です。そのため、通常のシートをお尻の形に合わせて立体的にして、ベルトでしっかり固定し安定させる、という工夫もあります。
もっと詳しく
雪のない季節は、スキー板の代わりにローラーを付けて練習します。本番シーズンに向けて、選手たちはこのローラー仕様で舗装された道をストックで漕ぐことでバランスや腕の筋力を保ち、基礎体力を鍛えています。

ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会を観戦するときは、選手のスピードや身体の使い方はもちろんのこと、座り方の違い(ひざ立ち、正座、長座位)、シートの形にも注目してみると面白いかもしれません。
教えてくれた人

text by TEAM A
photo by Hiroaki Yoda,Takamitsu Mifune