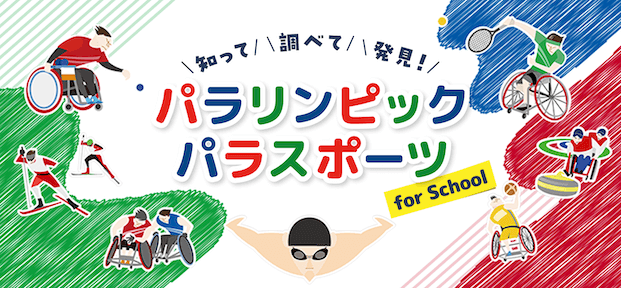福島県、誰もいなくなった村を自転車ロードレースで復興。世界大会の予選開催で各国のサイクリストも注目!

東日本大震災で大きな被害を受けた福島。そんな福島をサイクリングで盛り上げ、復興をアピールしていこうという主旨でスタートしたのが“ふくしま復興サイクルシリーズ”だ。海や山、さまざまな地形を楽しめると多くのサイクリストが注目するこのイベントは、どんなものなのか。大会事務局スタッフでアドバイザーを務める自転車ジャーナリスト・橋本謙司氏にお話をうかがった。
福島の復興に、なぜ自転車ロードレース?

東日本大震災の想像を絶する被害の記憶は、もちろん私たちの胸にしっかりと刻まれているが、その後の復興については時間がたつにつれて報道される機会も段々少なくなり、被災地から離れていれば意識することも減っていく。そんな流れを食い止め、復興をアピールするとともに、福島県を訪れる人を増やそうという取り組みがある。その鍵となるのが自転車だ。
「津波と原発事故という深刻な複合災害を経験した福島浜通り地域で初めて開催された自転車イベントが、葛尾村で開催したロードレース“ツール・ド・かつらお”でした。5年以上にわたる全損避難を経て、2016年に一部地域を除き避難が解除され、翌2017年に誕生しました。このイベント以降、福島県浜通り地域を中心に、福島県内各地で“震災復興”と“交流人口拡大”を目的として、スポーツ自転車を趣味にする市民サイクリスト向けの自転車レースイベントが次々に誕生していきました」(橋本謙司氏、以下同)
福島県浜通り地域を中心に年間10レース近く開催される自転車レースが、2023年にはシリーズ化され“ふくしま復興サイクルシリーズ”という名前がついた。2025年シーズンは、4月19、20日の“ツール・ド・かつらお”に始まり、11月16日の“城 d’ 白河(ジロ・デ・シラカワ)”で幕を閉じる。中でも浜通り地域全体を舞台にして開催される超広域ロードレース“ツール・ド・ふくしま”はシリーズ最大規模のレースとなる。初開催を目指した2023年は大雨による災害で無念の中止になったが、2024年は無事に実施され、多くのサイクリストを福島に呼び込んだ。復興のアピールといえば、いろいろな形があると思うが、なぜ“自転車”だったのだろうか。
「今も震災の爪痕が多く残る浜通り地域は、主に15市町村にまたがる広域です。それらの地域をつないで復興を後押しできるツールが、スポーツ自転車です。スポーツ自転車は誰でも100kmほど走れるようになれます。エリアが広い浜通り地域全体の振興を目的としたとき、自転車イベントがこの地域にはマッチしていました。13市町村が舞台になるツール・ド・ふくしまは、その象徴的な大会でもあります。
また、福島の自然豊かな地形も理由のひとつです。海と山、福島には浜風を感じるシーサイドコース、標高1500m超の坂を登る山岳コースもあり、各地域で異なる地形を楽しめます。また福島には、自転車競技部のある高校がいくつかあり、昔から自転車競技が盛んな地域であったことも大きいですね。過去にオリンピック選手を複数輩出し、著名な競輪選手も活躍しています。福島県古殿町出身の窪木一茂選手は、パリオリンピックの自転車トラック種目に出場し、世界選手権では優勝しました」
誰でも気軽に参加できるサイクリングで、県外からの参加者も増加

趣味であっても、レースと聞くと敷居が高く感じるかもしれないが、ふくしま復興サイクルシリーズには、タイムや順位を競うレース部門とは別にサイクリング部門がある。レース部門も、上級者から初級者までレベル別に分かれているので、誰でも安心して参加できる。
「イベントは、レースとサイクリングという2つのカテゴリに分けられています。たとえば、4月開催の“ツール・ド・かつらお”はロードレースですが、6月開催の“そうまサイクリング”は、その名の通りサイクリングであり、各エイドステーションでは現地ならではの食事や銘菓のふるまいもあり好評です。本格的なレースとして勝負を楽しみたい方から、仲間や家族とサイクリングを楽しみたい方まで、年齢は10代から70代まで、幅広い層が参加できるシリーズとして展開しています」
また、大会のほとんどが土日の2日間で開催されるのも特徴的だ。つまり、参加者は現地での宿泊も込みで参加することになり、食事や宿泊で地元の人と交流を深めることができ、交流人口の増加に繋がる。
「6月に開催する川内村のイベントは、土曜日に“かわうち高塚高原ヒルクライム”、日曜日に“かわうち山岳ライド”と、レースとサイクリングを1泊2日で楽しんでもらえます。土曜日夜には、バーベキュー大会を開催し参加者・主催者みんなで盛り上がり、翌日のイベントに参加するという良い流れができていると思います」
長距離を高速で移動できるスポーツ自転車ならではの特長を生かした浜通りの復興サイクルイベント。レースからサイクリングまで幅広いサイクリストを受け入れるイベントを用意し、“震災復興”と“交流人口拡大”を推し進めている。ここ2年ほどで県外からの参加者も段々増えてきており、迎える地元の人々の熱も回を重ねるにつれて高まっているそうだ。
福島から世界挑戦への道がひらける

この“ふくしま復興サイクルシリーズ”に先ごろ吉報がもたらされた。福島浜通り地域等15市町村を舞台にした超広域イベントである“ツール・ド・ふくしま”が、2026年大会からアマチュアサイクリストたちの憧れである世界的ロードレース“UCIグランフォンド・ワールドシリーズ”の予選大会(世界で約30大会ある)に加わることが決定したのだ。
「“ふくしま復興サイクルシリーズ”の目的は日本各地からたくさんのサイクリストを呼ぶこと。復興の地に足を運んでもらい、サイクリングを通して福島県の今を知り、過ごしてもらうことです。その起爆剤になるのが “ツール・ド・ふくしま”のUCI(※1)グランフォンド・ワールドシリーズ加入でした。半年以上の関係機関との調整を経て、晴れてUCIグランフォンドの予選大会に決定(※2)したわけですが、これで何が起きるかというと、日本全国からはもちろんのこと、世界のサイクリストから注目される存在になるということです。実際、今年9月の“ツール・ド・ふくしま”大会は来年に向けたプレ大会にも関わらず昨年の3倍以上のエントリー数があり、その注目度の高さを感じています。この大会を勝ち抜くことによって、市民サイクリストにとって世界一の舞台とも言える世界選手権(チャンピオンシップ)に出場できます。福島から世界へ。そして海外から福島へ。震災から14年が経ち、街は急速に生まれ変わっている一方で、震災の爪痕は当時のまま至る所に残り、浜通りには光と影が存在しています。だからこそ、大会参加をきっかけに福島の今を見て感じてもらい、この地域について自ら考えてもらうことは大事だと思います。“ツール・ド・ふくしま”をはじめとするふくしま復興サイクルシリーズの各大会には、そういう価値があると考えます」
(※1)国際自転車競技連合
(※2)ツール・ド・ふくしまのUCIグランフォンド・ワールドシリーズ加入は、2026年大会からであり、2025年9月6~7日開催の今年の大会は来年に向けたプレ大会としての開催になる。2026年大会は6月12~14日に開催予定。
橋本氏はスポーツ自転車の専門家であり、ふくしま復興サイクルシリーズのアドバイザーとして、各大会のコース設計をする際に実際に自転車で現地を走る。その際、特に原発事故による避難指示区域だった大熊町、双葉町、浪江町などを巡ると、前回はなかった道が新たに通っていたりと変化がめまぐるしいそうだ。整備された道は、自転車でも走りやすくなっている。
「イベント参加者と話をすると、イベント参加をきっかけに震災後初めて(福島を)訪れたという人も多いですね。とても走りやすいし、立ち寄りやすいカフェや宿も多く、また来たいという声を聞くととても嬉しくなります。一方、ロードレースは交通規制を伴うため、地元の皆さんにはレースへのご理解とご協力が不可欠です。そんな中で、自転車のロードレースなんて初めて見るという小さな子どもや高齢の方が、朝早くから旗を持って応援してくれたりする光景を見ると、イベントを実施する価値を感じます。また、国土交通省がサイクルツーリズムの推進のため、一定の要件を満たしたサイクリングルートを“ナショナルサイクルルート”に選定するという制度があるのですが、浜通り地域はその候補に挙がっています。このような明るい話題もあわせて、今後も自転車で、福島をどんどん盛り上げていきたいですね」
東日本大震災による津波や原発事故の影響で、住み慣れた場所から離れなくてはならなかったり、長い時間をかけて変わり果てた街を再建していったりと、福島は本当に多大な苦悩、負担を経験してきた。しかし今、それを乗り越え、“復興”を発信する鍵のひとつとなっているのがサイクルロードレースだ。来年、世界規模のロードレースシリーズの予選大会が開催されれば、世界中への発信にもなる。世界中からより多くの人々が福島を訪れることになるだろう。
text by Reiko Sadaie(Parasapo Lab)
photo by Kenji Hashimoto