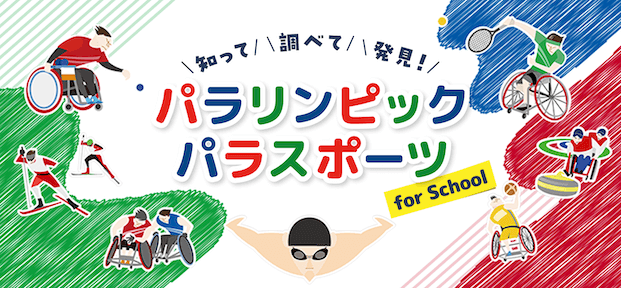「平和都市・広島でプレーする意味を実感」Bリーグ・広島ドラゴンフライズの“ヒロシマプライド” スポーツを通して伝える平和の尊さ

80年前に人類史上初めて原子爆弾が投下された広島。今も原爆ドームや平和記念史料館には国内外から多くの人が集まり、平和を発信する都市の役割を担っている。その広島を拠点とするプロバスケットボールリーグBリーグの「広島ドラゴンフライズ」は、スポーツを通して平和を伝えるためのチーム運営を行っている。その根底にある「HIROSHIMA PRIDE(ヒロシマ プライド)」とはどのような考えなのか、元プロバスケットボール選手であり、広島ドラゴンフライズの代表取締役社長を務める浦伸嘉氏に伺った。
負けて相手を憎んでいては争いしか生まれない

ホームでの試合に敗れた広島ドラゴンフライズの選手たちは、起立したままファンとともに拍手で相手チームの退場を見送った。
スタンディングオベーションで相手チームを見送り試合を締めくくる。これはドラゴンフライズのホームゲーム特有の光景だという。
「ラグビーで言えばノーサイド。試合で熱く戦った後でも相手をリスペクトする気持ちは忘れない。憎しみからは争いしか生まれないですからね」と浦氏は話す。
元選手である浦氏は、負けた後の悔しさで選手たちに同情するところはあるという。「正直、負けた直後は一刻も早くその場から立ち去りたいですし、アウェイでの試合はそれができるのが普通です。ですが、悔しくても相手を称え、恨んだりしない。負けた時こそ、自分たちが成長しようというところに意識をつなげていくことが重要です。負けても相手を恨まず、発展を目指す。広島の先人たちの考え方をこのクラブから発信していきたいんですよね」
広島ドラゴンフライズは、復興を遂げた広島の「屈しない魂」と「歴史に学び未来を切り開く情熱」を込めて「HIROSHIMA PRIDE(ヒロシマ プライド)」というスローガンを掲げ、様々なアクションを行っている。スタンディングオベーションは、まさにその象徴的な取り組みだ。
選手たちがつなぐ平和への願い「#おりづるリレー」とは

広島ドラゴンフライズは、スポーツと平和をつなぐプロジェクトをいくつも手がけている。
その代表的なものの一つが、2018年から始まった「ピースプロジェクト」だ。テーマは「平和があるからこそのスポーツ、スポーツがあるからこその平和」。ホームゲームの試合開始前に両チームで折り鶴の交換をしたり、試合で最もフェアプレーをした両チームの選手を表彰する「おりづる賞」の授与をしたりしている。
フェアプレーは一見平和につながっていないように見えるが、相互に相手のことを尊重することが平和につながると浦氏は考える。「戦争とは違い、スポーツはルールの中で競い合い、相手をリスペクトします。そうしたスポーツの理念を体現したのがフェアプレーです。競争するという点で同じでも、全く性質が違う。フェアプレーが広がれば戦争のような争いはなくなっていくはずです」
他にも2021年からはBリーグのチームの選手らが折り鶴を手にしながら平和のメッセージをつなげていく「#おりづるリレー」というSNS企画も始めた。
投稿は広島に原爆が投下された8月6日から終戦の日にあたる8月15日という象徴的な期間に実施。多くの人に戦争や平和というテーマを身近に感じてもらおうという狙いがある。
昨年は、自分が考える平和とは何かや、自分が平和のためにできること、心がけていることなどについてSNS上でそれぞれの思いを語っていた。
「この企画は地元の高校と一緒に企画しました。賛同者がどんどん増えていて、Bリーグの全チームが参加してくれているだけでなく、同じ広島を本拠地とするプロ野球チームの広島東洋カープ、サッカークラブのサンフレッチェ広島の選手なども協力してくれています」(浦氏)
リレーは海を越え、アメリカ、NBAのコーチらも参加。浦氏は更なる広がりと企画のブラッシュアップを考えているという。
「広島の印象が変わった」移住してきた選手たちの思い

広島ドラゴンフライズの選手は全国各地、海外からも集まっているが、彼らは広島ドラゴンフライズに入団後、広島で暮らすようになり、この土地、そして平和について何を感じているのだろうか。
2021年から広島ドラゴンフライズでプレーする、司令塔の寺嶋良選手はこう語る。
「広島ドラゴンフライズに加入してから、広島という街に対する印象は大きく変わりました。まず、街の規模感がちょうどよく、生活がしやすい。少し車を走らせれば自然にも恵まれていて、オンとオフの切り替えがしやすい環境です。そして何より、広島の人たちは本当に温かく、クラブや選手に対して親しみを持って接してくれます。
また、広島といえばやはり、“平和を大切にする文化や取り組み”がとても印象的でした。資料館や原爆ドーム、8月6日の原爆の日の式典などを通して、平和の尊さや命の重みを改めて考える機会を持つことができました。
僕たち選手も、スポーツを通じて『平和のメッセージを届ける』という役割を意識するようになり、プレーに対する責任感や使命感がより強くなったと感じています。クラブとしても、おりづる賞やおりづるリレー、平和に関する啓発活動など、地域と連携しながら“広島らしさ”を大切にしている点に深く共感しています。バスケットボールをするだけでなく、“平和都市・広島”という特別な土地でプレーする意味を、年々強く実感しています」(寺嶋良選手)
アメリカ出身で、Bリーグの他チームを経て2021年から広島でプレーするニック・メイヨ選手も、広島でプレーすることに特別な思いを抱いているようだ。

「広島は素晴らしい町で、自然も多く、過ごしやすいです。そして何より、出会う人たちがみんな親切で温かく、とてもフレンドリーに接してくれるのが印象的でした。平和を祈ることの意義は、国や文化の違いを超えて、互いを理解し、リスペクトし合い、そして日々の生活や人生そのものに感謝する気持ちを持つことだと思います。この広島という特別な土地で、仲間と共にバスケットボールができることを、心から誇りに思っています」(ニック・メイヨ選手)
平和のヒントに。世界から注目される日本

「バスケットボールは素晴らしいスポーツだと思っています。常に味方同士でコミュニケーションを取る姿だったり、敵味方問わず、相手が倒れた時に手を差し伸べて起こす文化だったり。相手へのリスペクト、配慮、協調性を学ぶことができる点で、世の中の紛争などの問題を解決するヒントになるのではないかと思っています」(浦氏)
また、バスケットボールを広島で行う意義についても強調する。
「バスケの発祥はアメリカ。太平洋戦争で日本が戦ったのもアメリカです。そんな歴史を経て、今こうして日本でアメリカの選手とも共にバスケットボールをできていることは、スポーツの力のひとつを示していると思っています。広島だからこそ発信できる平和の意味をこれからも模索しながら伝えていきたいと考えています」(浦氏)
戦争や平和について考えるきっかけを与える役目は、広島だからこそ説得力を持ってできるはずという気持ちが伝わってきた。浦氏のお話の中で、広島を代表するプロスポーツチームの広島東洋カープは、市民球団として戦後復興の道を地域とともに歩んできたという話があった。戦後80年を迎える今、野球だけでなくバスケットボールからも、平和の尊さは広島から確かに伝えられている。
text by Taro Nashida(Parasapo Lab)
写真提供:広島ドラゴンフライズ