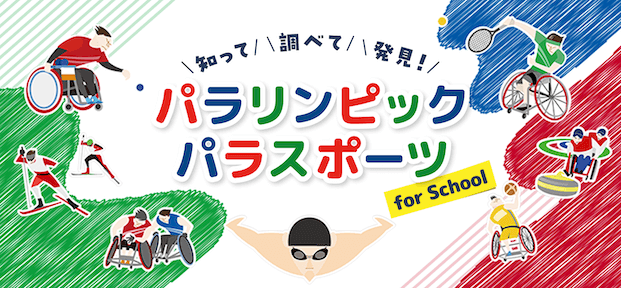-
-
Sports /競技を知る
-

-
【佐藤友祈×親野智可等対談】好きを伸ばしてくれた恩師に再会。金メダリストの原点になった「いかかいじゅう」とは?

パラ陸上・佐藤友祈を世界のトップたらしめていることの一つは、「のめり込む力」ではないだろうか。そのベースは静岡県藤枝市立広幡小学校2年生で、当時担任だった親野智可等(杉山桂一先生)に出会ったことで培われたと、佐藤は語る。佐藤に影響を与えた杉山先生の教えとは。すべての子育て世代に送るアスリート×恩師対談。
佐藤 友祈(さとう・ともき)|車いすプロアスリート
1989年静岡生まれ。東京2020パラリンピックの陸上競技で2冠。パリで400m種目で銀メダルだった悔しさを糧にトレーニングを続け、今秋インドで開催された世界選手権で金メダルを奪還した。小学2年生のときにハマっていたのは、けん玉。「先生にほめてもらった思い出があります」。モリサワ所属。

親野 智可等(おやの・ちから)|教育評論家
1958年生まれ。公立小学校で23年間教師として務めた後、教育評論家に。けん玉を取り入れたのは、「子どもでも練習すると新しい技がどんどんできる。リトルサクセスを積み上げて、自己肯定感を上げるのに最適と思ったから」。本名、杉山桂一。

ほかの大人とは違っていた杉山先生
佐藤と、小学2年生のときの担任だった親野智可等こと杉山先生が母校で再会。あの1年間のことはいまでも忘れられない、と佐藤は振り返る。
佐藤友祈(以下、佐藤):今日はよろしくお願いします。
杉山桂一(以下、杉山):久しぶりだね。こちらこそよろしくお願いします。
佐藤:早速ですが、小学生ながらに杉山先生は子どもを「ほめて伸ばす」ことを大切にされていたのがすごく印象的で。いまでも僕が一番思い出す先生といえば、杉山先生です。もちろん悪いことは悪いと叱ってくれるんだけど、「わかるよね」みたいな注意の仕方で、他の大人とは違っていました。

杉山:ありがとうございます。ただ私もね、若いころは力が入りすぎちゃって否定的に叱っていたこともあったんだよ。「だめだろ」「こんなことでどうするの」って。
佐藤:全然、想像できません。
杉山:そのせいで、クラスの雰囲気が悪くなっちゃった。それで猛省して、もっと言葉を大事にしようと気持ちを切り替えて赴任して来たのが、この学校だったんだよ。
佐藤:それは知りませんでした。
杉山:以来、何かあったときは、まずしゃがんで子どもと目の高さを合わせて、「どうしたの」「そうか」と共感的に言い分を聞くようにして。こちらから言うべきことがあるときは、「わかった。だけど、これはこうだからいけないよ」と言うように心がけていたんだよ。もっとも、友祈くんは叱るようなことをする子ではなくて、大体ニコニコしていたけどね。
佐藤:僕がすごく覚えているのは、授業中に描いたイカの絵。タイトルは「いかかいじゅう」なんですが、その絵を先生がすごくほめてくれたおかげで、自信につながったんですよ。
杉山:そうなんだ。(絵を見て)動きがあるし、画用紙からはみ出しているでしょ。2年生ぐらいだと、普通は枠の中に収めようと思っちゃうから、なかなかこうは描けないんですよ。この絵は、わが教師人生の中でも最高の絵かもしれない。
佐藤:めっちゃほめてくれる(笑)。この絵は両親が額に入れて、いまでも実家に飾ってあります。その後、絵画教室にも通ったんです。
杉山:そうだったんだ。それはいい循環だね。ちなみに、この名前とタイトルの文字、私が書いたんだけど、きれいでしょ(笑)? 文字を書くのが苦手で、先生になってから一生懸命練習したんだよ。
佐藤:先生のおかげで、好きなことを見つけてチャレンジするようにもなれたと思っています。当時、歌も好きだったのですが、自分には可能性があるんじゃないかと思えるようになって、地域の合唱団に入ったりもしたんですよ。
杉山:自分で好きなことを見つけて取り組む、それ自体が幸せなことだし、自己肯定感も高まります。そういう経験をしている子どもは、大人になってからも自分がやりたいことを自分で見つけてどんどんやる、という生き方ができるようになるんです。まさに友祈くんのようにね。

「根拠のない自信」で一歩前へ
杉山先生にほめられた経験が、好きなことにチャレンジする原動力になったという佐藤。自分を信じて突き進む姿勢は、パラスポーツに出会ったことで一気に開花した。
佐藤:先生と関わったことが強く活きているなと思うのが、パラリンピックと出会ったことです。20歳で突然車いす生活になったのですが、23歳のとき、テレビ放映していたロンドンパラリンピックで三輪の車いすで競技をしている選手たちを見て、めちゃめちゃかっこいいなと思い、僕もこの競技でこの舞台を目指そうと決めました。
杉山:そうだったんだ、すごいじゃない。
佐藤:競技を始めるにあたり、競技用車いすメーカーにアプローチしたんです。「次のリオパラリンピックに出場して金メダルを獲る佐藤友祈です。僕にレーサー(陸上競技用車いす)をサポートしてください」って。
杉山:すごいね。
佐藤:もちろん相手にされませんでした。だから、両親に頭を下げてレーサーを購入してもらって、大会に出て。タイムはいまより全然遅かったけど、好きだから時間を忘れて打ち込むことができた。自己ベストが伸びるにつれてポジティブな感情がどんどん脳の中を占領していって、「僕には才能があるんだ」と思えたし、「リオに出て金メダルを絶対獲るんだ」みたいなところまで、自分の中で一気に話が飛んだんです。
杉山:何かを成し遂げる人は、根拠のない自信があって、「できる」と思えるんだよね。
佐藤:まさにそうです。
杉山:その背景には、やっぱりほめられた経験があるんじゃないかな。やる人は放っておいてもどんどんやるし、それで幸福度も上がっていく。友祈くんも幸せでしょ?
佐藤:はい。いまはだれもやったことのないことをやりたいとも思っています。例えば、先日の代表合宿に子連れで参加したのもその一つです。世の中ではまだ、父親は子どもの世話を「手伝う」みたいなところがある。でも僕は、「いやいや、自分の子どもでしょ」って思うんです。だから、僕が発信することで、世の中の雰囲気を変えていきたい。
杉山:こういうのが大事なんだよ。立派だよ。
佐藤:ありがとうございます。先生と出会えてよかったです。

人は、好きなことをやるために生まれてきた
苦手なことを克服させたい、または本人のためと思って敷いたレールの上を走らせたいという保護者がいるかもしれない。しかし、それには弊害しかない、と杉山先生は断言する。
杉山:注意したいのは、子どもに苦手なことを克服させようとすることです。片づけや朝が苦手だとか、嫌なことは後回しにする、というのは、そもそも生まれつき。子ども本人に直そうなんてモチベーションはありませんから、はっきり言って、親の育て方やしつけでは変わりません。
佐藤:そうなんですね。たしかに、僕も苦手なことには向き合ってこなかったです。
杉山:ところが、親がどうにかしようと思っちゃうと、叱る回数が増える。すると、子どもの自己肯定感はボロボロ、親子関係も悪くなる。そして、やってみたいことがあっても、「どうせだめだろうな」と思って、一歩を踏み出せない大人になっちゃうんですよ。
佐藤:僕の競技でいうと、最初に取り組んだのが、400mと1500mという好きな種目でした。でも、パリ大会のメダルイベントから1500mが除外されたんです。リオ、東京とメダルが2個ずつだったのに、パリで1個になるのがどうしても嫌だったので、大っ嫌いだった100mもやろうと決めた。いまでは嫌い、苦手という感情がどんどん薄れていっています。
杉山:自分で決めたことだから、がんばれるんだよね。片づけや時間管理も、大人になって達成したい夢や目標ができて、そのために必要ならできるようになるんです。それと同じだよね。
佐藤:僕も「自分がやってやるんだ」って主体的に動いたことで、初めて切り替えることができたと思います。
杉山:習い事や受験だって、本人が主体的に取り組むことがめちゃくちゃ大事です。なぜなら、子どもの人生は子どものものだから。いまだに勝手にレールを敷く親がいるんだけど、それは子どもの人生を搾取していることになるんです。人間は、自分が「好き」「やりたい」と思ったことを自分からどんどんやっていくのが一番幸せだし、そのために生まれてきたと思うんだよ。だから、親は監督やコーチではなく、応援団であってほしいよね。
佐藤:僕も、改めて杉山先生にたくさんほめてもらったり、両親に応援してもらったからこそいまがあるんだと、つくづく思っています。杉山先生は僕の恩師です。本当にありがとうございます。

杉山先生と出会い、自分の「好き」にとことんチャレンジできるようになったおかげで、佐藤は日本を代表するパラアスリートとなった。「ほめる」「応援する」ことがいかに大切か、佐藤の生き様が体現している。
【金メダリスト×恩師対談】パパアスリートも悩んでる! 佐藤友祈が教育評論家・親野智可等に教えてもらった、子どもへの声かけのコツ
https://www.parasapo.tokyo/topics/126296
text by TEAM A
photo by X-1