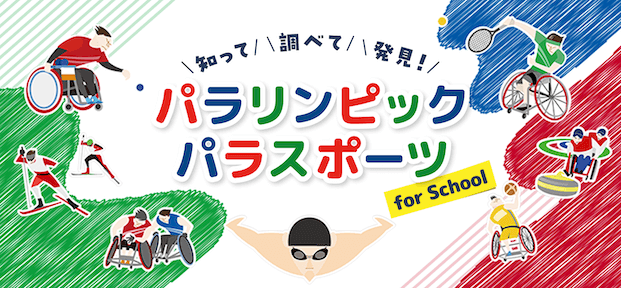-
-
Sports /競技を知る
-

-
【未来教育】20年後、子どもたちが世界で活躍するために、知っておくべき「インクルーシブ」な考え方とは?<前編>

昨今、子どもへの教育改革が盛んに行われている。その中枢にあるものがグローバル化だ。これまでの常識が通用しなくなると言われている10年後、20年後は、主体性を持って多様な人々と協調するスキルがますます必要となるだろう。そこで今回はカナダ在住のパラリンピック金メダリストで、国際パラリンピック委員会及び国際オリンピック委員会の教育委員会メンバーを務めるマセソン美季氏に、今、私たち大人が知っておくべき、そして未来を生き抜く子どもたちに伝えておきたい「インクルーシブ」な考え方について話を伺った。
「世界のスタンダード」なマインドに、日本は乗り遅れている!?

編集:まず、表題の「インクルーシブ」な考え方を問う前に、現在私たちが目指すべき社会と言われ、徐々に広がりを見せつつある「インクルーシブ社会」というものがありますが、その意味について教えていただけますか?
マセソン美季(以下、マセソン):もともとインクルーシブとは「包括的な、全てを含んだ」といった意味合いになりますが、インクルーシブ社会とは、あらゆる人が排除、孤立せずに安心して暮らせる社会と言われています。私は、公平性が担保され、あらゆる人に活躍の機会が与えられる社会だと思っています。
編集:あらゆる人とは、全ての人、ということですよね?
マセソン:そうですね。国籍、文化、障がいの有無、セクシャリティなど、これまで区別されがちだった枠を無くし、ひとり一人を尊重する社会を目指そう、ということです。現在、これが2016年から2030年までの国際目標として掲げられている「SDGs(持続可能な開発目標)」の取り組みの一つにもなっていることもあり、世界的な動きとして注目されています。
そんな社会作りに欠かせないのが、今回のテーマである「インクルーシブ」な考え方。それはつまり、あらゆる人に対して先入観や固定観念を持たず、人間の多様性を許容できるオープンなマインドと言えますね。
編集:なるほど。目指してはいるものの、日本ではまだまだ当たり前とは言えない部分も多いですよね。マセソンさんは、カナダ・オタワに在住されていて、お仕事でも世界各国を飛び回っていらっしゃいますが、海外と日本ではそれぞれどれくらい「インクルーシブ社会」は根付いていると思われますか?
マセソン:例えば私は車いすユーザーですが、カナダにいる時は、特に妙な視線を感じることはありません。私のようなアジア人も障がい者も『当たり前の存在』なんですね。かたや母国である日本に帰国すると、ジロジロと見られることが多いですし、一般の人と区別されたり、車いすに乗っているだけでぎこちない対応をされることも少なくありません。それで、「あ、そういえば、私って障がい者だったんだ」と改めて気づかされるんです。
特に日本は、北米と比べると街中で障がいのある人を見かけることが圧倒的に少ないから視線を集めやすいのかもしれませんが、そんな周囲の反応に居心地の悪さを感じて、障がいのある人はますます外に出なくなってしまうのではないかと思います。うちの子供が日本に来たときに、街中で見かけるのが健常者で若い人ばかりだから「みんな、日本のテクノロジーで治してもらったんだね。お母さんも治してもらったら?」と言っていたくらい(苦笑)。
私自身いつも同じ車いすで様々な国を移動していますが、自分が障がい者であることを忘れる国と痛感させられる国がある。私の障がいや能力云々じゃなくて、その国の環境や社会を構成する人によって障がいを感じる度合いが変わるんですよ。
編集:日本は、よくも悪くも昔から「みんなと同じ」を良しとする文化がありますよね。日本人が「違い」に対して過剰に反応してしまうのは、やはり移民を多く受け入れている欧米などに比べて、人種や宗教、文化など、様々な「違い」を日々感じることが少ない国だからでしょうか。
マセソン:環境の差はあるでしょうね。あとは、教育の差も大きいと思います。特に昔は障がいのある子どもは普通校ではなく養護学校に通っていて、学校生活で障がいのある子と接することはほぼ無かったんですね。今は特別支援学級などがあり、一緒に過ごせる時間も少しづつ増えてきましたが、やはりまだまだ障がい者を身近でリアルな存在に感じる環境は限られているのではと感じています。それに、学校でもメディアでも「かわいそうな人だから助けてあげましょう」とか、障がいのある人は困っている。という歪んだ考え方の刷り込みは、まだまだ残っていますしね。
例えば、息子が通っていたカナダの幼稚園では、逆に先生から私に「どんどん学校に出入りしてください」と頼まれたことがありました。教科書で教えるのではなく、実際に障がいのある人と同じ空間を共有することで、自然な学びを促していたんだと思います。障がいのある人たちに対する接遇のマナーなんか一切教えません。一緒にいろんな体験をすることで5歳児だって、自ら気付いて「美季が来るときは、床に散らかっているものを片づけておかないと車いすで通れないよね」とか、自然と考え方や行動が変わっていきます。そして絶妙なタイミングで必要な時に手を貸してくれるようになるんですよ。
そういった経験の違いが顕著に現れたのが、日本と北米の子どもたちに、インクルーシブな社会とはどんなイメージか、を絵で描いてもらったとき。
日本の子どもたちの絵は、手を繋いで輪を作っている人たちの真ん中に障がいのある人がポツンといてみんなで守っているイメージ。それに対して、北米の子どもたちの絵は、障がいのある人や高齢者、様々な人種の人たちでひとつの輪を作っているイメージになりました。
日本はマジョリティ(多数派)を指して「みんな」という言葉が使われているように感じることが多いけれど、インクルーシブな社会ではマイノリティ(少数派)も含めた全ての人が「みんな」なんですよ。
インクルーシブな考え方で、発想やアイデアが何倍も広がる

編集:日本と北米の子どもたちが描く絵の違いからも感じられますが、こういった教育の違いで、子どもたちの将来においてどんな可能性の違いが生まれると思いますか?
マセソン:インクルーシブなマインドが幼い頃から身についている子どもたちは、自分と違う人やモノ、コトにも抵抗が少なく理解を示しやすいと言えるのではないでしょうか。世の中には色々な人がいて様々なニーズがあるということが大前提になっていれば、将来自分がサービスやモノを提供する側になったときも、発想が柔軟で豊か。先入観や固定観念に邪魔されることなく、多角的にイメージしてアイデアを生み出すことができるのでは、と思います。
編集:確かに画一的だったり、みんなと同じ感覚に慣れていると、発想が偏りがちになりますね。
マセソン:想定外のことが起きたり、規格外の人に出会ったりしたときにパニックになってしまう、というのもありますよ。車いすユーザーの客に慣れていないお店に私が行くと、スタッフが慌ててしまう、というのも残念ながらまだよくありますね。
編集:日本人がよく言われる、道で外国人に道を尋ねられた時にアタフタしてしまうのとすごく似ていますね。
マセソン:そうそう。外国人が日本語で質問しても「I don’t speak English」と言って、逃げてしまったり(苦笑)。
編集:外国人もそうですけど、障がいのある方をはじめ、あらゆる人と小さな頃から関わることは、コミュニケーション能力の育成にも繋がる気がします。どんな人とも物おじせずに話せるようになるといいますか。
マセソン:そう!人との関わり方の土台に、より幅が生まれると思います。多様な人と関わることで、上記のようなシチュエーションでも動じない強さも育つのではないでしょうか。
面白い話があって、うちの犬が小さかったときに、犬のしつけ教室で「いろんな種類の人に会う」という宿題が出たんですよ。外国語を喋る人、自転車に乗っている人、工具をジャラジャラと身に付けている人など、とにかく飼い主と違う特徴を持つ人たちと出会い慣れていくことで多様性に対する享受の幅を広げていくことが目的だったんですけど、これって、人間も同じことが言えるんじゃないかなと、すごく興味深かったですね。
小さな頃からあらゆる人と日常的に関わることで、子どもたちのインクルーシブマインドの差は歴然。この意識の積み重ねは、当然子供たちの今後の“人間力” の形成にも大きな影響を与えるだろう。<後編>では、実際に日常でどのように「インクルーシブ」な考え方や感覚を身につけていくかをマセソン氏にインタビュー。乞うご期待。
この記事の<後編>はこちら↓
【未来教育】コミュニケーション力、柔軟な発想力が育つ「インクルーシブ」な感覚の身につけ方 <後編>
https://www.parasapo.tokyo/topics/16472
この記事の<後編>はこちら↓
【未来教育】コミュニケーション力、柔軟な発想力が育つ「インクルーシブ」な感覚の身につけ方 <後編>
https://www.parasapo.tokyo/topics/16472
PROFILE
マセソン美季
1973年、東京生まれ。東京学芸大学1年のときに交通事故で脊髄を損傷し車いす生活となる。1998年長野パラリンピック、アイススレッジスピードレースで金メダル3個、銀メダル1個を獲得。大学卒業後は、多くのパラリンピック選手を輩出してきたイリノイ州立大学へ留学。現在は、国際パラリンピック委員会(IPC)及び国際オリンピック委員会(IOC)の教育委員会メンバーを務めながら、日本財団パラリンピックサポートセンターのプロジェクトマネージャーとして勤務。パラリンピック教育を通じてインクルーシブな社会をつくるため、教材作成、普及啓発活動に取り組む。カナダ在住。2児の母。
1973年、東京生まれ。東京学芸大学1年のときに交通事故で脊髄を損傷し車いす生活となる。1998年長野パラリンピック、アイススレッジスピードレースで金メダル3個、銀メダル1個を獲得。大学卒業後は、多くのパラリンピック選手を輩出してきたイリノイ州立大学へ留学。現在は、国際パラリンピック委員会(IPC)及び国際オリンピック委員会(IOC)の教育委員会メンバーを務めながら、日本財団パラリンピックサポートセンターのプロジェクトマネージャーとして勤務。パラリンピック教育を通じてインクルーシブな社会をつくるため、教材作成、普及啓発活動に取り組む。カナダ在住。2児の母。
Interview by Parasapo Lab
Text by Uiko Kurihara(Parasapo Lab)
Photo by Takeshi Sasaki