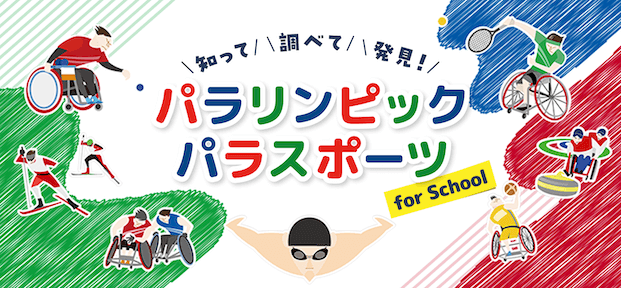北海道日本ハムファイターズを小学生が夏休みの読書で応援?本を読んで観戦ができる驚きの企画とは

北海道日本ハムファイターズは、夏休みに読書をした小学生とその家族を球場に招待するプロジェクトを行っている。今年で9年目となる企画で、昨年はなんと道内7割弱の自治体の図書館が参加するなど、着実に広がりを見せている。一見、関係のなさそうな「野球」と「読書」だが、なぜファイターズはこの企画を始めようと考えたのか、考案した株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントの荒木龍史さんに伺った。
本を読むことで野球観戦ができる

このプロジェクトの名前は「本を読んでファイターズを応援しよう」。道内の小学生が夏休みに図書館で本を借りて目標の数を読み終えると、オリジナルのシャープペンシルがもらえるほか、抽選でエスコンフィールドHOKKAIDOでの観戦チケットが当たる。
企画には北海道教育委員会などが加わり、全道から参加する図書館を募る。参加した図書館は、夏休みに入るまでの期間、子どもたちから申し込みを受け付ける流れだ。
申し込みをした子どもたちには進捗状況を書き込める「読書通帳」が渡され、そこに借りた日とタイトルを記入していく。返却時に図書館に通帳を持って行くとチェックマークがつけられ、その本を読んだ証となる。 目標達成のために読む本は、特に定められてはいない。北海道青少年育成協会が出している「*北海道青少年のための200冊」などを参考にしながら自由に選ぶことができるため、子どもは本を読むことに義務感を感じることなく自主的に取り組める。

目標冊数は学年に応じて変わる。1、2年生であれば10冊。3、4年生は8冊。5、6年生であれば6冊となる。なぜ高学年になるほど冊数が少なくなるのだろうか。
荒木さんは「元々は高学年になればなるほど冊数を多くする方向でしたが、教育委員会さんなどいろいろなところからお話を聞くと、高学年になるほど長い本をじっくり読むというのが指導要領になっていると知ったんです。そのため、目標冊数は今のようになりました」と語る。
昨年チケットに当選したのは150組600人。1人の児童が家族を3人までスタジアムに連れていくことができた。
荒木さんは「ファイターズでは他にも観戦チケットをプレゼントする企画はありますが、この企画のチケットは動員率が70%ほどあって、他の企画よりも10%くらい高い傾向にあるんです。お子さんががんばって手に入れたチケットですので、少し足を伸ばして試合を見に行こうというご家族が多いのかもしれませんね」と話す。
*北海道青少年のための200冊:2025年から「こどもたちに読んでほしい200冊」に名称変更
企画のきっかけは北海道の学力低下?

この「本を読んでファイターズを応援しよう」はどのように始まったのだろうか。
元々ファイターズでは、道内の読書習慣を促す「グラブを本に持ちかえて」という取り組みを2014年から行ってきていた。これまでに、選手の推薦本をまとめたリーフレットの作成や読まなくなった本を回収して図書館に寄贈するブックシェアリングを実施。寄贈数は11000冊を超えたという。
2015年には球団自ら幼児向けの絵本も制作。タイトルは「もりのやきゅうちーむふぁいたーず」。ファイターズ選手たちが、それぞれの個性に合った森の動物に変身して野球チームを結成し、ライバルの海の野球チーム「おーしゃんず」と熱い戦いを繰り広げる物語だ。
このように読書に力を入れてきたファイターズ。そうした中、荒木さんは北海道の子どもの学力が低下していることを知り、読書を通してこの問題の解決に協力できないかと考えた。
「私自身も子どものころによく本を読んでいて、それが今につながっていると感じています。球団として少しでも子どもの読書習慣の向上に貢献することで変化を起こせないかと思いました」
こうして「本を読んでファイターズを応援しよう」は始まった。

「図書館からすると、どうしても業務が増える側面はありますが、たくさん参加してくださり感謝しています。初参加以降ずっと継続して参加してくださっている図書館もあれば、残念ながら参加が途切れてしまったところもあります。広い北海道でどれくらいの自治体でこの企画が行われたのかが一目でわかるよう、2024年に参加した自治体を青、2024年以前に参加したことのある自治体を緑で塗った地図を作成しました。見ていただいて分かるように2017年と比べると白い部分がかなり少なくなってきています」(荒木さん)
実際、2017年開始時の参加自治体数は89で、読了児童数は416人だったが、2024年は113自治体が参加し、読了者数は846人と倍増。着実に北海道に浸透してきている。
荒木さんは「影響したのかどうかは分からないですが、2017年に41位だった全国学力試験の順位は37位に若干上昇しました。少しは影響してくれていればうれしいですよね」と笑った。
読書→野球。野球→読書。広がる子どもたちの体験の幅

「本を読んでファイターズを応援しよう」は、学力向上の目的だけでなく、ファイターズや野球に興味を持ってもらうきっかけ作りにもなると荒木さんは見ている。
「参加する図書館にはファイターズのロゴ入りのポスターが貼られます。普段図書館に行っていて、あまりスポーツに興味がない子にも関心を持ってもらえるのではないでしょうか」(荒木さん)
そして、もちろん「ファイターズの試合を見たいから読書をしよう」という子どももいるだろう。読書と野球は一見つながりにくいが、だからこそ、どちらかにしか興味のない子が両方を体験するきっかけになる。実際、このプロジェクトで本を読み終えた子どもの多くが野球の観戦を希望している。というのも、本を期間中に読み終えた児童は自動的に抽選に応募するようになっていない。読了後に図書館からもらえる情報をもとに、任意で応募することになっているが、ここで応募する児童の数は7割~8割にもなるという。
エスコンフィールド移転初年度の2023年は、チームの成績も低迷していたために9月の座席の確保は容易だったというが、好調だった昨年は難航したそうだ。荒木さんは「今年もきっと昨年と同じようにシーズン終盤に好調なファイターズが見られると思います。すでに席数は確保していますので、ぜひ夏に本を読んで応援に来てください」とアピールする。
プロ野球チームが地元地域の読書習慣や学力問題に課題感を抱き、アクションを起こすという本プロジェクト。それは地域の課題解決だけでなく、球団としても、元々野球に関心のある層以外にも球団のことを知ってもらうきっかけとなるだろう。こうしたスポーツチームとホームタウンの交流による相乗効果に、今後もますます期待したい。
text by Taro Nashida(Parasapo Lab)
写真提供:©H.N.F.