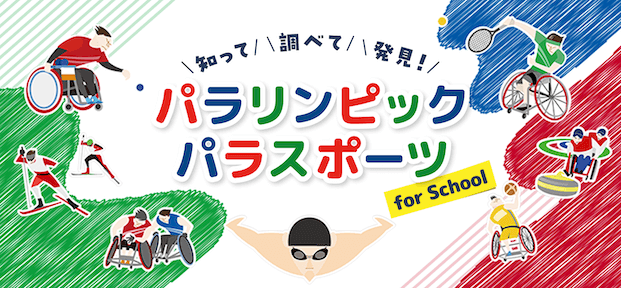アート×サッカー×農業を体現する、唯一無二のサッカーチーム。FC越後妻有が地元住民と目指す、新たなスポーツの形

全国から新潟の越後妻有(えちごつまり)地域に移住し、農作業や芸術祭の運営をしながらチームの活動を続ける「FC越後妻有」の選手たち。本稿前編では「大地の芸術祭」プロジェクトの概要とFC越後妻有との関係性、そしてアマチュアスポーツ界の抱えるセカンドキャリア問題について紹介した。後編では、選手たちの1日のスケジュールや、具体的な取り組みについてを取り上げ、地域の人々との関わりやその影響力に迫る。
「アート×農業×サッカー」。三足のわらじを履く選手たちの毎日

FC越後妻有の選手たちの生活は、午前中に農業をはじめとするNPOの仕事、午後はサッカーの練習、というスタイルが基本。平日はサッカーと仕事をバランスよくこなし、週末には試合に臨む。試合のない土日は、終日農作業をすることもあるそうだ。
たった2人の選手から始まったチーム発足当初は、仕事内容が棚田の保全のみだったため「農業とサッカー、二足のわらじを履くチーム」と紹介されることも多かった。しかしメンバーが増えた今は、農業をする選手もいれば、芸術祭の観光ツアーを手伝う選手、食に携わる選手、アート作品の管理を担う選手もいて、その職務範囲は多岐に渡る。「農業にももちろん人手が必要ですが、僕たちには、越後妻有の地域を持続可能な形にしなければならないという使命があるんです」と元井監督は言う。FC越後妻有はもはや「農業×サッカー」を超え「アート×農業×サッカー」という新境地に挑んでいるのだ。
MF(ミッドフィルダー)のポジションを務める山下由衣選手が越後妻有の地に移住したのは、5年前。サッカー選手として活動しながら、NPOで責任のある仕事を任されることについてこう語る。「サッカーは何年もやってきたことなので、体に染み付いていて、私にとっては当たり前というか。でもNPOの仕事は、越後妻有に来てから初めて経験することも多く、常に緊張感があるんです。サッカー関係者以外とコミュニケーションを取ることもほぼなかったので、難しさはありながらも、日々勉強だなと感じます。今サッカーをしながら社会勉強ができているのは、自分にとって間違いなく大きなプラスになっています」

農業はというと、今まで経験したことがない分、やはり大変さを感じているという。重い機械を押して、全身泥まみれになりながら田んぼの中を歩く「溝切り」という作業をした際は、あまりの過酷さに泣いてしまったそうだ。
「でも、おいしいお米ができるのは、苦労した過程があってこそ。お米を食べたみんなが『ありがとう』と言って喜んでくれるので、大変よりもやりがいの方が大きいですね」と山下選手は笑う。毎年気候が違えば、お米の育ち方や田んぼの環境も異なるため、一筋縄ではいかない。いつも同じ方法で成功するとは限らず、自分で試行錯誤を繰り返しながら工夫しなければならないのは、米作りもサッカーも同じだ。
お互いのために、何ができるのか。チームと地域が自然と助け合う

「越後妻有に来た当初は、長くても2年ぐらいかなと思っていましたが、いつの間にか5年も経っていました(笑)」と山下選手。この地にずっといたくなる理由はほかでもなく、地元の人々の温かさだ。「いつも熱心にFC越後妻有を応援してくれますし、仕事をやっている姿も見守ってくれる。いろいろなところで気にかけていただいていて、私たちにとっては家族のような存在です」
FC越後妻有は「おじいちゃんおばあちゃんの笑顔を作り出す」というコンセプトのもと活動しているが、実は選手たちの方が満たされていると感じることも多いのだそうだ。
「チームでは『FC越後妻有が地域のために何ができるのか』を考え、地域の方々は愛情をもって、練習場に採れたての野菜を差し入れてくださる。雪国という土地柄もあるのか、助け合いの精神のようなものがとても自然に根付いていると感じます。選手たちが素敵な住民の皆さんとの交流で成長していく様子を近くで見られて嬉しいですし、これが地域に根付いたサッカーチームのあるべき姿じゃないかな、と思うんです」(元井淳監督)
また、3年前からは地元高校生との関わりも。雪深い十日町の高校のスキー部では、冬になると長期でスキー合宿を実施するため、その間は体育教員が不在になる。FC越後妻有の選手や監督が、体育教員の代わりに他の生徒へ授業を行っているそうだ。
「大地の芸術祭」の総合ディレクターである北川フラム氏からは、常々「地域の御用聞きのような存在でありなさい」と声をかけられているというが、まさに日常の中で自然とそれを体現しているのだろう。
応援してくれるサポーターも、実に幅広い。サッカーファンはもちろんのこと、選手が農作業をする姿を見て「あなたたちが頑張っているなら応援に行こう」という地元の人々や、もともと芸術祭のファンだったことをきっかけに活動を知った人など、さまざまな層がいる。
その中でも、試合に応援にきてくれるのは、やはり地元のおじいちゃんおばあちゃんが多い。ホームゲームの駐車場には、農業を切り上げて観戦に訪れた何台もの軽トラが停まっているのがお決まりの光景だ。アウェイゲームには車で遠征をして、試合の帰りに、ご当地の美味しいものを食べて帰ってくる。地元の人たちにとっても、FC越後妻有は日常を彩る存在になっているのだ。
FC越後妻有の存在意義を忘れず、地域と共に歩み続ける

もちろん、サッカーチームとしての躍進も止まらない。
「チームとして足りないものはまだまだありますが、なでしこリーグ参入という目標も、少しずつ現実味を帯びてきたところです。地元の皆さんには『遠くに行ってしまうようで寂しい』なんて言っていただきますが、僕らはおそらくほかのどのチームよりも『地域の皆さんと同じ船に乗っている』という意識が強い。地域との繋がりや、FC越後妻有の存在意義、根底にあるものは決して変わりません。もっともっと強くなって、この地域にいる子どもたちにも、サッカーを頑張ろうと思ってもらえれるような存在になれればうれしいですね」(元井監督)

越後妻有地域への想いを、山下選手はこう語る。「十日町を代表する棚田と言われている『星峠の棚田』を初めて見たとき、この美しい場所を守っていかなければ、と直感的に思ったんです。越後妻有で自然に囲まれながら地元の人と関わって、価値観も変わったし、何よりも人生が豊かになったと感じています。私たちがこの場所で生活しながら、サッカーをする姿を見せることで、若者からの関心も高まって、一緒に農業してくれる人がもっと増えてほしいと願っています」
雪深い冬を越え、春には田植えをし、夏は祭りやアートでにぎわい、秋には黄金色の棚田が広がる。そんな暮らしの中でサッカーに打ち込むFC越後妻有の選手たちの姿は、地域の日常にすっかり溶け込んでいる。今後も人と人とのつながりを何よりの力にしながら、地域とチームが一緒になって未来を描く、新しいスポーツの形を体現していくだろう。
text by Miu Tanaka(Parasapo Lab)
写真提供:FC越後妻有