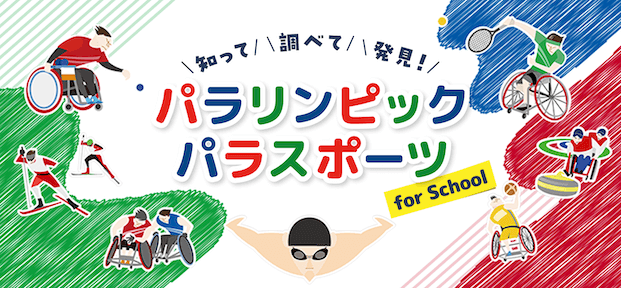沖縄の子どもたちの“体験格差”はどうしたら埋まるのか。FC琉球が打ち上げた「#日本一のスタジアム花火」

沖縄県は、全国で最も子どもの多い地域だ。しかし、離婚率や経済的な理由などにより、子どもたちが「心が動く体験」に触れる機会には大きな差があると言われている。FC琉球は、そんな“体験格差”の存在に向き合い、1000人を超える親子をスタジアムに招待。そこには、スポーツチームとして地域とどう向き合うかという、FC琉球なりの答えがあった。
“触れる機会”をすべての子どもに。FC琉球が届けるプロスポーツの力

透き通るような美しい海と温暖な気候。リゾート地としても人気の沖縄だが、そんな華やかなイメージとは裏腹に、相対的貧困率全国ワースト1位、ひとり親世帯出現率全国ワースト1位など、実はさまざまな社会課題を抱えた地域でもある。
それらが生んだ課題の一つが、子どもたちの「体験格差」だ。「体験格差」とは、環境によって子どもが得られる体験に格差が生じること。つまり、家庭環境や経済状況のために、習い事や旅行、文化体験やスポーツに大きな差が出ることを指す。
そんな沖縄の子どもたちの体験格差緩和に向けて、さまざまな取り組みやイベントを行っているのが、沖縄唯一のJリーグクラブ・FC琉球だ。たとえば、小学生以下はホームゲームの全試合を無料で観戦できる。また、クラブに所属する選手やそのOBは、積極的に県内の小学校を訪問し、体育の授業に参加したり、サッカーを教えたりして、沖縄の子どもたちが少しでもプロスポーツに触れられる機会を作っているのだ。
「体験格差」の問題は、スポーツや文化だけに限った話ではない。観測史上2度しか雪が降ったことのない沖縄には、雪をそもそも見たことがない子どもたちも多いという。彼らが雪と触れ合う機会を得られるようにと、人工降雪機を使い、スタジアムの場外で雪まつりを開催したこともあった。
日本一のスタジアム花火。1万人が同じ体験をする“特別な一夜”

このような取り組みの一つとして、昨年初めて開催された大イベントが「#日本一のスタジアム花火」だ。実はFC琉球に限らず、全てのJリーグ加盟クラブは、社会貢献活動や地域保全活動の実施を理念としている。FC琉球の場合、先に述べたような沖縄特有ともいえる社会課題を踏まえて、県民やサポーターに喜んでもらえるような集客イベントを企画しているのだそうだ。
「#日本一のスタジアム花火」のそもそもの目的は、夏の試合の集客。普段サッカーに触れない人にもスタジアムに足を運んでほしいと企画されたものだった。さらに、体験格差を埋める一つのきっかけになればと、沖縄のひとり親家庭の子どもや、離島在住の子どもなど、さまざまな環境にある沖縄の子どもたちを無料で招待した。スタジアムで試合を観戦した後、ピッチに入り、みんなで花火を見上げるのである。
そもそもJリーグの試合を開催するには、一定の基準を満たす必要がある。沖縄県内で、収容人数や設備面での基準を満たすスタジアムは、FC琉球がホームスタジアムとして使っている沖縄県総合運動公園陸上競技場のみ。つまり、離島で試合をしたいと思っても、それは現実的ではないのだ。離島の中でも比較的アクセスがいい石垣島や宮古島には、国内外から有名な選手が訪れることがあるが、それ以外の離島の場合、子どもたちがプロの選手と触れ合える機会はほぼないという。アクセスの悪さだけでなく、島に小学校が一つしかなかったり、子どもの数が少なかったりするのもその理由だ。
このイベントを担当した、FC琉球マーケティング担当の川崎さんはこう語る。「夏の集客試合に訪れる人の数は、約1万人。1万人が同時に楽しめるコンテンツって、よく考えたらなかなかないんです。雪まつりの時は、数十人ごとに交代制で雪を体験してもらったのですが、花火なら、夜空にバーンと打ち上げれば、そこにいる全員が同じ感動をシェアできる。それは来場者だけでなく、試合が終わったばかりの選手も含めてです」
イベントには、離島に住む29組の親子に加え、ひとり親世帯の支援団体を通じて100人ほどの子どもたちが招待された。FC琉球の試合を見てサッカーに興味を持ってもらえるのはもちろんだが、川崎さんはそれ以外の部分も含めて、開催意義を強く感じたという。
「サッカーの試合直後に、さっきまで選手たちがいたピッチに入れることを喜んでいた子が多かったです。芝生にみんなで寝転んで、花火を見てもらって。離島で育った子どもの中には、花火を初めて見たという子もいました。親御さんからも、今回の企画のおかげで子どもに貴重な体験をさせてあげられて良かった、という声をいただいて、胸が熱くなりましたね」(川崎さん)
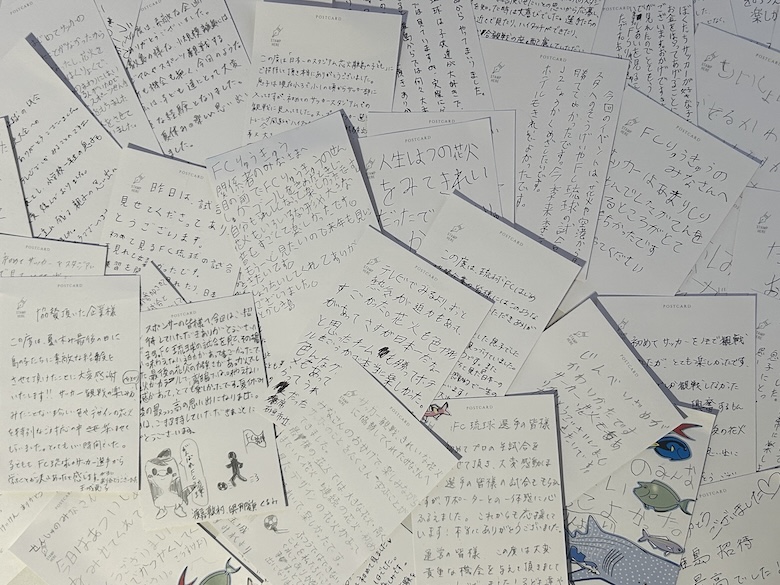
子どもたちにとって、サッカーの全てになりうる。FC琉球の責任

Jリーグの試合というと、チームのグッズやユニフォームを身につけた熱狂的なサポーターが、大きな声でチャント(サポーターが試合中に歌う応援歌やコール等)を送る……という光景を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、FC琉球のホームゲームは、観客の6割が家族連れで、なんともアットホーム。他県のチームとは全く雰囲気が異なり、子どもたちの歓声が響くスタジアムなのだそうだ。これは全国でもかなり珍しい光景だと川崎さんは言う。全国1位の出生率を誇り、今なお子どもの数が増え続けている、沖縄ならではともいえるだろう。
負けている試合の最中でも、客席の子どもたちから「FC琉球!FC琉球!」というコールが巻き起こる。もちろん試合に出場している選手にも届いており、子どもたちのコールにつられて選手たちが声を出して、全体の士気が上がることも多々あるという。選手が子どもたちにとって憧れの存在であるのと同時に、選手もまた、応援してくれる子どもたちに支えられているのだ。
先にも述べた通り、FC琉球は沖縄で唯一のJリーグクラブだ。首都圏であれば、東京ヴェルディ、浦和レッズ、川崎フロンターレなど多くのクラブがあるが、沖縄にはFC琉球しかない。
「FC琉球を通して経験したことが、子どもたちにとってのサッカーの全てになりうる。そういった意味で『沖縄には僕たちしかいない』という責任もあるんです。都会の子どもが当たり前に体験できることを、沖縄にいるから体験できない、なんてフェアじゃない。沖縄にいるからこそ体験できることももちろんたくさんありますが、FC琉球が地域を代表するクラブとして果たせる役割は大きいのではないかと思っています」(川崎さん)
スタジアムの空に再び咲く花火が、子どもたちの夢のスタートラインに

多くの離島から成る沖縄の特性上、体験格差を完全にフラットにすることはなかなか難しい。
川崎さんは「FC琉球にできることは、1回のイベントでなるべく多くの人に価値ある体験を届けること。試合を生で見て、その激しさや熱気を体感して、みんなで花火を見上げて、何かを感じ取ってもらえたら嬉しいですね。その1回が一生忘れられない経験になって、子どもたちが何か夢を持つきっかけになれば、それは素晴らしいことだと思います」と語る。
2025年8月23日(土)には、2回目となる「#日本一のスタジアム花火」が開催される予定だ。子どもたちがみんなで遊べる場外ゲームを企画したり、沖縄の離島の魅力を伝えるブースを設置したりして、1回目よりもさらに絆や繋がりを感じられるイベントを企画しているという。
「普段は出会うことのない子どもたち同士が、バックグラウンドに関係なくコミュニケーションを取って『来年もまた一緒に花火を見ようね』と約束できるようなイベントにしたいんです」と川崎さん。イベントの内容自体ももちろん魅力的だが、背景にある沖縄の社会課題を知ることで、また異なる視点を持って楽しめるのではないだろうか。
FC琉球のFW9 浅川隼人選手も、少年時代に選手と触れ合った体験が、サッカー選手を目指すきっかけになったそう。沖縄の多くの子どもたちが選手やクラブと触れ合うことで、いつかプロサッカー選手になりたい、サッカーを続けたい、FC琉球とともに歩んでいきたいと思ってほしいと語る。「#日本一のスタジアム花火」の開催は、子どもたちの夢のきっかけづくりのためにも、大きな役割を果たしているのだ。
text by Miu Tanaka(Parasapo Lab)
写真提供:FC琉球