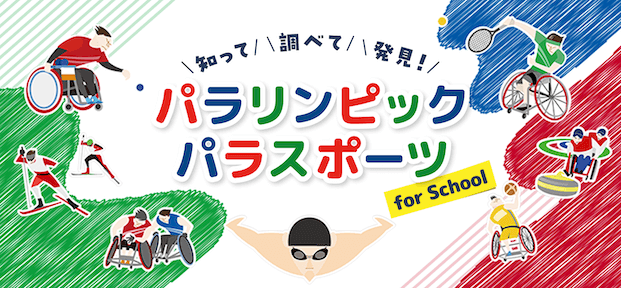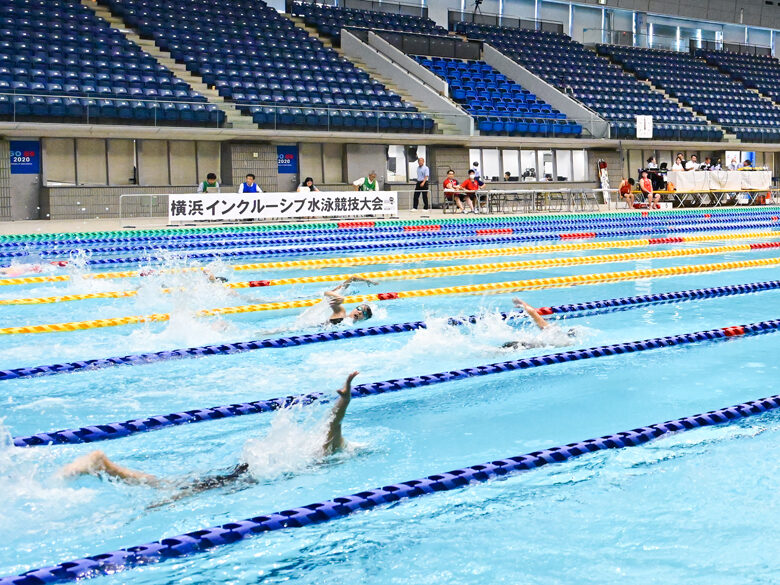-
-
Sports /競技を知る
-

-
-
-
Athletes /選手プロフィール
-
未来のトップアスリートも真似したい! 水泳・金メダリスト鈴木孝幸を支える食事術

何を、いつ、どれぐらい、どのように食べるか。体が資本のアスリートにとって、食事はパフォーマンスに直結する重要な要素だ。一方でスポーツをがんばる子どもたちの保護者からは、どうしたらよいかわからないと悩む声が聞こえてくる。料理好きを自認する水泳・鈴木孝幸がその腕前を披露しながら、スポーツ栄養士とともに栄養の基本を語った(※)。
※本記事は、パラスポーツを応援する人を増やす東京都のプロジェクト「TEAM BEYOND」の小学3~6年生親子向けワークショップ「パラアスリートと料理教室 おいしく食べて強くなろう!」から構成しました。
少ない食材が続けられる秘訣
日々、ハードなトレーニングに取り組んでいる鈴木孝幸(以下、鈴木選手)。集まった小学生の親子に、食の重要性をこう伝える。
「トレーニングで疲れるので、いっぱいご飯を食べて栄養をとりつつ、睡眠もしっかりとって回復に努めています。食事はとっても大事です」
「大人になって料理をするようになってから、料理が好きになった」と語る鈴木選手の得意料理の一つが麻婆豆腐だという。

©Tokyo Metropolitan Government
「いろいろなものが食べたくて、なるべく少ない食材で続けられそうなものから作っているのですが、麻婆豆腐はお店のものや市販の素だと、わたくしにはちょっと辛するぎるんです。でもレシピを探したら、しょうゆやみそなど家にある調味料でできるし、辛さも調節できる。しかも、作ってみたらおいしかった。以来、よく作る料理の一つになっています」
鈴木選手が実際に使っているレシピで、調理の様子を披露。指が欠損している右手で食材や瓶、フライパンなどを押さえたり支えたりし、3本の指がある左手で包丁やレードルをつかんだり、瓶のふたを開けたりする。

©Tokyo Metropolitan Government
「(鷹の爪ならぬ)タカの爪を使ってもいいけど、指を切ったら……」
「『今日は大好きな子に会うから口臭くなりたくないぞ』というときは、ニンニク少なめにする(笑)」
鈴木選手は、場を和ませながら作業を進める。

©Tokyo Metropolitan Government
とりわけアスリートらしさが感じられたのは、豆腐の選び方だ。約10年前から鈴木選手の栄養指導を行い、競技生活を支えてきた公認スポーツ栄養士の鈴木志保子氏(以下、志保子先生)はこう説明する。
「豆腐には木綿豆腐と絹豆腐がありますが、いわば絹豆腐は豆乳を固めたもので、木綿豆腐はそこにおからが入っているイメージ。木綿の方がより栄養価が高いので食の細いお子さんにはおすすめですし、豆腐ステーキなどほかの料理にもアレンジできます。料理によって使い分けてみて」

©Tokyo Metropolitan Government
仕上げに垂らすごま油の量もポイントだ。
鈴木選手は、こう語る。
「以前、先生に栄養調査をしていただいたことがあるのですが、1週間の食事をすべて写真に撮り、体重を記録したことで、何食べたらちょっと太るといったことがなんとなくわかるようになりました。麻婆豆腐も最初はレシピ通りに作っていたのですが、ちょっと体重が増えたなとか、お腹が疲れてるなというときは、油の量を調節したりしています」
志保子先生も、アドバイスする。
「食が細く、エネルギーをもっととりたいお子さんには、ちょっとごま油を加えることでカロリーアップするといいですよ」
苦手な野菜は?
麻婆豆腐とともに披露したのが、ブロッコリーとトマトのサラダ。実は野菜が好きではないという鈴木選手のために、志保子先生が伝授したレシピだという。

©Tokyo Metropolitan Government
「イギリスに住んでいたころに教わりました。これだけ食べておけばいいと先生が言ったから、以来、今に至るまで毎日作っています。(何を作ろうかと)迷わない」
志保子先生は説明する。
「野菜の種類が多いレシピだと食材を用意しても使い切れず、キュウリがキュウリじゃないみたいな状態になってしまいます。その点、ブロッコリーは冷凍できますし、トマトは生でも日持ちする。しかも、どちらもほぼ世界中にある食材なので、どこに行っても食べられます」
レシピといっても、レンチンしたブロッコリーとくし切りにしたトマトを一緒に器に盛るだけ、と簡単なのもいいところ。
「実はわたくし、ブロッコリーは茹でるよりもレンチンが好きでございまして。茹でると栄養が逃げてしまいますので、いつもこうやっております」と鈴木選手が言えば、「(ブロッコリーに含まれる)ビタミンCは水に溶けるので、茹でるとビタミンCが茹で汁に出てきちゃうんです。だからもれなく(栄養を摂りたい)と考えると、レンチンの方がいい。なべを洗う手間も省けます」と志保子先生。
これに白飯を添えることで、バランスのよい一食のできあがりだ。

©Tokyo Metropolitan Government
食の基本は「学校給食」
いまでは鈴木選手は自分の体の栄養士といえるほど知識と技術を身につけていると、志保子先生は太鼓判を押す。
「以前はちょっと体を大きくしようかとか、いろいろなことにチャレンジしていた時期もあったのですが、今はもうほぼ固定した状態。何より、私以上に自分の体のことをよく理解していて、何をどう食べたら体がどう反応するかわかっているので、世界のどこに行ってもほぼ大丈夫です」
鈴木選手も食事づくりのベースにしているのが、食事の基本構成だ。スポーツ栄養では、エネルギー源とたんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルのバランスが重要とされている。要は、①主食(ごはん、パン、麺)、②主菜(肉、魚、卵、豆・豆製品)、③副菜(野菜)、④乳・乳製品(牛乳、ヨーグルト)、⑤果物 を毎食そろえればよい。
「すべてそろえると、自分の体にとっていいものがちゃんと入ってきて、タカみたいな丈夫な体が作れますし、泳ぐのも速くなったりします」
ちょっと難しそうと感じる場合は、学校給食を参考にするといい、と志保子先生。
「学校給食はみんなの頭の中を整理するための構成になっています」

©Tokyo Metropolitan Government
小学生の場合、おやつをどうするか、という問題もあるだろう。鈴木選手はケーキなどのスイーツは食べず、ご褒美としてヨーグルトにはちみちをかけたりする程度。小学生の場合は、食事をきちんと摂ったうえで、エネルギーが足りない場合は、おやつとしてスイーツやお菓子を食べるものいいそうだ。
小学生の保護者からは、少食や偏食を気にする声も聞かれたが、志保子先生は、発育のピークの時期にしっかり食べられるようにすることが大切とアドバイスする。
「個人差はありますが、基本的には中学に入ってから一生懸命食べても手遅れになる可能性があるので、小学4年生ごろからきちんと食べられるようにして」

©Tokyo Metropolitan Government
痩せ志向にも警鐘を鳴らす。
「身長が伸びれば、その分エネルギーが必要になるので食べる量も増やさなければいけません。にもかかわらず、食べる量を控えると栄養状態が悪くなって身長が伸びにくくなりますし、貧血や疲労骨折、女子の場合は初経遅延といった問題が起こり、一生苦労する体になる恐れも出てきます。そうならないためにも、1ヵ月に一度程度、身長と体重を測って成長曲線と照らし合わせてください。急激に身長が伸び始めたら、ほどほどの運動とよく食べてよく寝ることが大切。大きくなることにエネルギーを使いましょう」
パラアスリートの状態は十人十色。鈴木選手の場合、胃腸が丈夫である程度の量は食べられるが、両足が欠損している分、消費カロリーが少ないため、実際の食事量はこぢんまりとしたものになるという。そのギャップを踏まえ最適な食事を考えるのがスポーツ栄養の役割であり、見極めるには自分の目で本人を見るしかない、と志保子先生は語る。
食べムラや好き嫌いのある我が子に頭を抱える保護者は少なくないだろうが、スポーツ栄養の知識を踏まえつつ、我が子を見て都度、できることを模索する。その積み重ねが、アスリートのパフォーマンスを支えることにつながるのだろう。

©Tokyo Metropolitan Government
text by TEAM A
key visual by TEAM A